どうも、太陽です。(No18)
突然ですが、2020年9月12日での公開討論会での「菅さん、岸田さん、石破さん」の目指す国家像がボードに書かれて、表示されていました。
目指す国家像は以下です。
| ・ | 岸田さん。 | 「論語と算盤」 |
| ・ | 菅さん。 | 「自助・共助・公助 そして絆 規制改革」 |
| ・ | 石破さん。 | 「一人一人に「居場所」があり、一人一人が「幸せ」を実感できる国」 |
この中では「菅さんのキャッチフレーズが一番、しっくりくるというか、分かりやすいかな」と思いました。
2番目は石破さんですが、抽象的で、ぼんやりしているのがちょっと残念です。
3番目の岸田さんのは、「論語と算盤」の深い意味を知らないので、「分かりづらいなぁ」と思いました。
「論語と算盤」の意味は、以下を指します。
人間は「論語で人格を磨くこと」 と 「資本主義で利益を追求すること」 の両立が大切です、と説いた渋沢栄一の教育論とのことです。
なるほど!言われてみれば、「人格を磨くことと、資本主義で利益を追究することはどちらも大事だなぁ」と実感します。
「論語と算盤の意味」が国民に深く浸透しているとしたら、一番いいキャッチフレーズかもしれません。
ですが、「浸透率が低い」と思うので、普通の人は「どういう意味?」と疑問に思うでしょう。
では、「僕が目指す国家像のキャッチフレーズ」を紹介してみます。
「他の人が使わない、差別化した言葉」を使わないといけないので、考えどころですね。
1 僕が目指す理想の国家像とは?
僕の理想の国家像のキャッチフレーズは以下です。
「強い、面白い、優しい国」。
牛丼の「うまい、安い、早い」と同じ感じです。
具体的に深い意味を書きます。
まず、国家でも人でも、強くなければいけません。
強者が多くいればいるほど、国も国民も豊かになります。
それは精神的にも経済的にもです。
従来の日本での強みの分野、例えば、製造業やスポーツなどで「強さを追求する人はそのまま活かして活躍して欲しい」という意味です。
強いとは、例えば、シェアNO1企業や、利益率が上位の企業など、主に大企業が該当するでしょう。
大規模ではないですが、キーエンスのような企業も強いに入ります。
競争力が強く、そう簡単には潰れない企業であり、利益率やシェアが高い、または知名度も抜群にある有名企業も該当するでしょう。
アメリカでいえば、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)、さらにNetflixなどは当然、該当します。
中国でいえば、BATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)は該当します。
次に、面白さとは「従来の分野とは外れたところに、ニーズがある、ポテンシャルがあるのでは?」という視点から、提唱しました。
面白いとは、お笑いみたいな意味ではなく、ユニーク(独特)という意味合いが強いです。
(お笑いも日本を笑顔にしますけどね)
例えば、日本のアニメ・漫画・伝統の将棋など、興味深いジャンルはけっこうあります。
または、山口周氏によれば、強さとは「役に立つ」分野であり、日本企業の性能主義に該当します。
面白さとは「意味がある」分野であり、デザインや実用性とは遠いものに該当します。
(僕の解釈含みます)
スイスは「役に立つ時計」を作っていましたが、日本企業は「さらに安価で役に立つ高性能な時計」を作り始め、スイスは駆逐されかけました。
ですが、「意味がある」分野、つまりブランド系に走り、生き延びています。
カメラも、ライカやローライフレックスはブランドの代名詞ですが、性能で選ぶなら、日本企業のキャノンなどになるでしょう。
自動車も、性能で選ぶなら、トヨタなどになります。
ですが、ブランドなら、ポルシェなどになり、ヨーロッパ系が生き延びたのは「役に立つ」から「意味がある」という価値にシフトしたからです。
他の例では、バルミューダがあります。
他社製品なら2000円で買えるのに、2万円のトースターを売り出して、10年間で売上が1000%成長しているのです。
(ニッチな分野の深堀り作戦ですね)
加えて、このブランドを作るには、世界観が重要です。
さらに「各国の文化・思想・歴史などの背景・機微など」を詳しく知らないと、作れないのです。
詳しくは「世界観をつくる 「感性☓知性」の仕事術」に載っているので、読んでみてください。
さて、強い人もいて、面白い人達も多ければ、多様性が生まれ、国が豊かになり、「幸せな人も増えるのでは?」という提案です。
しかし、強さだけを追求する社会は息苦しいのです。
もちろん、強い人がいないと国は回りませんから、「かなり大事にしたい」です。
ですが、同時に「面白い研究や面白い人達も活かせる社会になればなぁ」という思いです。
最後に、優しいとは、以下の意味です
強い人がなるべく多くいて、面白い人もいる中で、競争ばかりだとギスギスした社会になるので、弱者やマイノリティにもある一定程度の優しさというか、「理解が必要なのでは?」ということです。
今後、AI時代においては、ホスピタリティの分野はけっこう活きます。
高齢化社会であり、介護分野も伸びるでしょう。
そういう意味で「優しさも忘れてはいけない」と思ったから、入れました。
人間的な能力(それを優しさと表現しました)は、AI時代においては価値が高まります。
ですが、そういう職種は労働集約型であり、規模の拡大が効きません。
ですので、人件費が大いにかかり、時間に縛られるので、給料が安くなりがちです。
もちろん、AI時代においては絶対的に必要な人達であり、人手不足になりがちな職種です。
ですが、「これが主産業になることはない」と思ったので、一番最後に位置づけました。
例として、介護、サービス業(飲食や観光など多数)、建築現場、教師、カウンセラーなどになります。
人間のコミュ力がかなり問われ、ホスピタリティ(おもてなし力)も求められがちな職業です。
加えて、「かなりヤバイ人達とは一定の距離を置くというのも仕方ない」と感じます。
「ヤバイ人達の居場所をどう確保するのか?」はけっこう課題だと思います。
ヤバイ人達とは、以下の本に書かれている人達のことです。
具体的には、以下になります。
1 生まれながらの障害。発達障害。
自閉症スペクトラム障害(ASD)
「脳はみんな病んでいる」という本によれば、以下のように書かれています。
本当かどうかは別として、「東大生の3〜4割は自閉スペクトラム症だ」と主張する人がいます。
著者も、東大卒でして、「経験からあながち間違っていない」と言っています。
「大学教授はそもそも全員発達障害だよね」と笑い飛ばす精神科の先生もいたそうです。
高機能自閉スペクトラム症の人は、知的な障害はありません。
少なくとも人口の1%程度はいて、東大や京大あるいは医学部に限ると少なくとも10%、人によっては30%以上該当するそうです。
高学歴はASDの巣屈なのですね。
さらに、この本の著者である、脳科学者の池谷裕二氏と、作家の中村うさぎさんが「自分たちはASDなのでは?」と疑っており、ドクターに診断を受け、結果まで載っているというおまけつきの本です。
気になる方は読んでみてください。
注意欠如・多動性障害(ADHD)
2 発達障害以外の精神障害。
パーソナリティ障害。
双極性障害(躁うつ病)
イーロン・マスクは「自分は双極性障害だ」と発表しており、偉人も稀に見かけます。
統合失調症。
3 後天的な脳の器質性の障害。認知症。
関わり方が詳しく載っており、非常に参考になります。
しかし、「本当に関わるのが無理だ!」と思ったら、浅い付き合いにすべきです。
病気の人達であり、可哀想ではありますが、仕方ありません。
自分までやられてしまいます。
他には、ダークトライアド(サイコパス、マキャベリスト、ナルシスト)、さらにサディストも該当します。
ヤバい人達を見分け、深く関わらないことが防衛策になります。
さて、仕事では本領発揮する人達もいるでしょう。
(仕事では能力面だけしか見ていないので、コミュ力のなさは分からないのです)
さて、石破さんは「一人一人の居場所を作る」と言いますが、けっこう難しいと感じますねー。
そして、この3つは順番が大事です。
「強さあってこその、面白さであり、その後の優しさ」なのです。
優しさが一番先に来ては国が持ちませんし、面白さが先に来てもニッチ過ぎるかもしれません。
だからこそ、強さが第一であり、次に面白さ、最後に優しさの順番になっています。
なるべくシンプルなキャッチフレーズにしました。
安倍元首相の「美しい国へ」という訳の分からないキャッチフレーズにはしません。
ところで、牛丼の「うまい、安い、早い」のキャッチフレーズも、けっこう変遷があります。
以下の記事に詳しいです。
https://www.shinoby.net/2016/09/8217/embed/#?secret=rXRVWYL6dL
吉野家は、いつから「うまい、安い、早い」に変わったのか?
https://dot.asahi.com/aera/2019073100014.html?page=2
吉野家「うまい、やすい、はやい」コピーが密かに並び替えられていた裏事情
やはり、外食産業での商売にとって、一番の重要要素は「うまい」でしょう。
次に、今の日本のデフレ下では「やすい」が来るのは仕方ありません。
最後に、「はやい」もニーズを捉えています。
シンプルですが、商売の全て・基本が詰まったキャッチフレーズなのです。
僕の国家像は「強い、面白い、優しい国」です。
強さが一番重要であり、国家の源であり、国力であり、日本が没落し、不幸になることを防ぎます。
次に、面白さがあれば、ユニークな立ち位置で、国家として存続できるかもしれません。
そして、日本国民も「ユニークな存在に価値がある」と認められれば生きやすくなるでしょう。
人口が将来的に8000万人レベルになるとすれば、ユニークな立ち位置も含めないと、生き残れなくなるかもしれません。
将来、強い国は、アメリカと中国、またはインドになっているかもしれませんね。
さて、この強さと面白さとは、実は経営戦略から発想が浮かんでいます。
ポーターの競争戦略です。
「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「集中戦略」になります。
「コストリーダーシップ戦略」は強者の戦略です。
「差別化戦略」は二番手企業などの戦略です。
「集中戦略」が弱者の戦略です。
「日本にもそのままある程度、当てはまる」と思いました。
強者はそのまま維持するか、増やし、差別化によって面白い人達も活躍し、弱者も「なんとか居場所を作る」という意味です。
弱者の居場所があることは、セーフティネットでもあり、国民の安心感へとつながります。
「強い、面白い、優しい国」って陳腐なキャッチフレーズだなぁと思われた方は、ここまで深い背景があることには気づいていなかったかもしれません。
昔から、3つにまとめるキャッチフレーズってけっこうありました。
例えば、KKD(勘、経験、度胸)は有名です。
他にも、QCDもあります。
QはQuolity(質)、CはCost(コスト)、DはDelivery(納期)です。
真・善・美もあります。
「真善美」とは哲学用語で、「人間の理想や追求目標となる普遍的な価値観」です。
「真」は学問や知性の、「善」は道徳や意思の、「美」は芸術や感性の、理想の姿を示す、そうです。
また、3つじゃ収まらず、4つにしたり、7つにするケースあります。
経営用語でいえば、例えば、4P(Product(製品・商品)、Price(価格)、Promotion(プロモーション)、Place(流通))になります。
有名な経営コンサルタント会社のマッキンゼーが提唱した7Sもあります。
特に、3つに絞り込む理由はないのですが、3つの方が語呂がいいのです。
2つだと、インパクトが弱いというか、伝わる量が減る印象があります。
例えば、僕の今回、提唱した「強い、面白い、優しい国」は、2つにすれば、「競争と共存」かもしれません。
「競争によって、強さを維持・拡大しつつ、共存によって、面白い人達、弱い人達も存在してOK」だからです。
ですが、これだと「具体的にどういう人達がOKなのか」不明です。
また、人によって、「強い、面白い」の後に違う言葉を選ぶ人もいるかもしれません。
例えば、「誠実な」などです。
「強い、面白い、誠実な国」だと、最後が「い」で終わっていないので、語呂が悪くなります。
もしくは、まったく違う3つの言葉を選ぶかもしれません。
菅さんは「自助・共助・公助」という3つを選びました。
良いキャッチフレーズだと思いますが、「どんな人材を必要としているのか?」は直接、伝わりません。
僕のキャッチフレーズはそのまま、必要な人材像をあぶり出しています。
「強い人、面白い人、優しい人」がいたら、いいのでは?という提案です。
もちろん、「3つとも併せ持った人」がいてもまったく問題ありません、というより、理想でしょう。
今回は「目指す国家像のキャッチフレーズをつけるとしたら、どうするか?」の僕の実験記事です。
僕は首相でも、政治家でもありませんが、挑戦的に考えてみました。
皆さんなら、どんなキャッチフレーズを作りますか?
このキャッチフレーズに「その人の人生観、個性が全て表れる」と僕は思っています。
もちろん、提唱したキャッチフレーズには深い意図があるかもしれませんが、それも同時に詳しく解説しないと、良さが伝わらない場合もあるでしょう。
最後に、今回の記事で載せた本を紹介して終わりとします。
ではこの辺で。(5724文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。





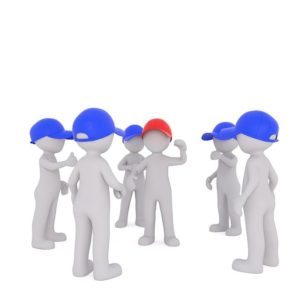




コメント