どうも、太陽です。(No12)
突然ですが、前回の記事が以下です。

成功・商売の法則PART2チーム編「あなたは商売で成功する物理学みたいな法則を知りたくありませんか?」
前回の記事で、1人の個人の成功・商売の物理学みたいな法則を述べました。
今回は1人の個人に焦点を当てるのではなく、「チームの成功・商売の法則」について述べます。
チーム、つまり企業などで商売の成功法則を知りたい方向けの記事です。
僕の今回の記事を読めば、「物理学に近い商売の成功法則みたいなモノ」の知識が手に入ると思われます。
興味がある人は続きをお読みください。
1 チームの例。
今までは1人の人間の成功・商売の法則を述べてきました。
ここからは個人ではなく、集団(チーム)について述べていきます。
突然ですが、個人のIQと集団的IQは違います。
(大前研一氏も「日本人の集団IQは低い」とよく言っています)
さて、ウーリー教授とMITの研究者の研究が以下です。
集団的IQは、チームメンバーの個人のIQは関係がなく、さらにチームメンバーのモチベーションの高さや個人の満足度もさほど重要ではないそうです。
では何が重要かというと、コミュニケーションの取り方です。
第一に感情のシグナルを読む個人の能力が平均より優れているチームは、作業を上手くこなしました。
第二に、少数のメンバーが会話を独占するチームよりも、メンバーが平等に会話するチームの方が集団的IQが高かったそうです。
つまり、優れたチームではみなが発言してお互いの意見を聞いていたのです。
第三に、女性のメンバーがいるチームは集団的IQが高かったそうです。
結論として、以下だと述べています。
個々のメンバーの能力はチームパフォーマンスの決定的要因ではなく、最近では重大な意思決定はチームで行うので、集団的IQを有効に活用すれば大きな利益が生まれ、うまく活用できなければ破滅的な結果を招きやすいと。
話を変えます。
今の時代、ノーベル賞ですら共同研究が当たり前でチームで成果を出しているのです。
「ノーベル賞は各分野の受賞者を3人まで」と決めており、弊害があるのです。
1990年代以降、世界に大きな影響を与えた発見は1人の天才の功績ではなく、大きなチームの功績です。
で、受賞者が3人までなので、功績から漏れるケースが出ているのです。
本にはプラシャーという「本来ならノーベル賞を受賞してもおかしくない人の事例」が書かれていますので興味がある人は読んでみてください。
本によると、「チームワークの功績を決めるのはパフォーマンスではなく、社会の捉え方だ」と述べています。
しかも「成功は社会的な現象だ」とも言っています。
また「チームの成功にはバランスと多様性が不可欠だが、功績を認められるのはひとりだけだ」と書かれています。
この本は研究者必読であり、功績を奪われたくないのなら、防衛策として読んでおいたほうがいいでしょう。
「ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした「成功の普遍的法則」という本です。
上記で述べた僕の考えた案を再度、載せてみます。
企業の事例。
1 「製品・サービスの質+ブランドイメージ」が「拡散力」によって売れるか決まる です。
これはチームの事例でしょう。
企業ですからね。
「製品・サービスの質+ブランドイメージ」は「何を」売るか?の部分であり、商品力です。
「拡散力」は「誰に」「どうやって」売るか?の部分であり、販促ですね。
商品をどう作るか?(企業で言えば商品ですし、政治家で言えば政策など、研究者チームであれば共同執筆物です)はチームのパフォーマンスで決まるのです。
ですが、そこでは集団的IQも関係してる可能性があり、そうであれば「コミュ力は重要要素」ということになります。
コミュ力がない人、または「会社の悪口を言いまくったり、チームの雰囲気を悪くする人が混ざるとチームのパフォーマンスが下がる」と予測されます。
いくら個人IQが高かろうが、または孤高の実力者であっても、チームという単位で成果をあげたいなら、加えるべきメンバーじゃないかもしれないのですね。
僕の場合、経営学というジャンルから、成功・商売の法則を編み出しました。
本の著者のアルバート=ラズロ・バラバラ氏は、「新ネットワーク思考」という世界的ベストセラーを書いています。
また、所属大学がボストンの名門ノースイースタン大学ネットワーク科学部門教授なので、ネットワークという専門分野から成功法則を考えたのでしょう。
バッググランドが違うと、世の中への捉え方が変わりますね。
2 強さの意味(チーム編)
ここで、強さについて深く考察してみようと思います。
「マーケティングプロフェッショナルの視点」という本から引用・まとめをします。
「悲しいから泣いているのではない。泣いているから悲しいのだ」という有名なフレーズがあります。
さらに「強いから勝つのか、勝つから強いのか」因果が不明です。
世界最速のF1ドライバーの実力伯仲争いであれば「速いから勝ったのか、勝ったから速いのか」判断が難しいです。
ですが、時代によっては勝敗の差が歴然としているのであれば「強いから勝てている状態」と言えるでしょう。
では、強いとはどういう意味かといえば、特定のスポーツを思い描いて列挙すれば、以下になるでしょう。
| 1 | プレーヤーに生まれつきの才がある。 |
| 2 | 経験を積んでいる。 |
| 3 | 練習を積んでいる。 |
| 4 | 仲間が優秀。 |
| 5 | チームに団結力がある。 |
| 6 | 資金が潤沢。 |
| 7 | 士気が高い。 |
| 8 | 休養十分で疲れていない。 |
| 9 | 対戦相手を研究している。 |
| 10 | 有利なポジションを取れている。 |
| 11 | 装備がいい。 |
| 12 | コーチがいい。 |
| 13 | 競技場を熟知している。 |
F1でもそれ以外のスポーツでも、ビジネスでも通用するでしょう。
ですが、もっと重要なのがこれらすべては目的達成のための「資源」だと理解できることであり、「強いとは資源をたくさん持っていること」だと言えることです。
「資源をたくさん持っている人が強い」のです。
また、「練習をし、勉強をし、準備を早く始めて時間を多めに持つことで強くなれる」といえます。
そして「戦いは数だよ」といいう有名なセリフがあります。
つまり、戦力、すなわち資源量が圧倒的であれば、無能が少しばかり戦略を間違えても、失策を許容できて、挽回可能なのです。
「戦力か、戦略か」というキャッチコピーがあります。
圧倒的な戦力があれば、目的の達成に戦略はいらない、考えられることを全部やれば勝てるのです。
しかし、「効率よく勝つ」という視点でみれば、このような「戦いは数」という勝ち方は褒められたものではありません。
「最小限の投資で目的を達成できるプロフェッショナル」を目指すべきであろう。以上、ここまで。
この本では人材(人財)は資源の中でも特に重要なファクター(要因)であり、優秀な人材の作り方に言及されているので、興味がある人は本をお読みください。
「強さとは資源量」という定義が興味深かったです。
確かに持ち球や武器が豊富であれば、勝ちやすくなります。
戦力が豊富であれば「戦略はさほど要らない」という言葉もよく聞かれることです。
本当に優秀な指揮官は戦力が乏しいのに、勝てる人なのです。
そこには戦力不足を補う優秀な戦略があったからです。
既得権益のTV局であれば圧倒的な優位性のある戦力(電波利権)を保有しています。
で、それに反抗しているのがN国党の立花孝志さんであり、YouTubeという武器で対抗しています。
立花さんがあそこまで善戦しているのはやはり頭がよく、戦略で戦力のなさを補っているのです。
そういう意味では立花さんの戦い方は弱者には参考になるでしょう。
また、野口悠紀雄氏の著書「超「超」勉強法」には以下のようなことが書かれていました。
(内容が多少、難しいので、興味ない方はスルーしてください)
必要条件と十分条件を理解すべし。
「語彙が多い人は大量の読書をした人だ」という命題が正しいとします。
すると、「語彙が多い人」という円の外側に「大量の読書をした人」という外円が囲むという関係になります。
「小さな円(語彙が多い人)」に入るためには、必ず「大きな円(大量の読書をした人)」に入っていなければなりません。
つまり、大きな円に入っていることが「必要だ」ということになります。
「小さな円(語彙が多い人)」に入っていれば、必ず「大きな円(大量の読書をした人)」に入っています。
だから、小さな円(語彙が多い人)は、大きな円(大量の読書をした人)に入るために「十分だ」となります。
もっとわかりやすく言えば、「人間であれば、必ず動物である」の関係は小さな円が人間、大きな円が動物になります。
動物であることは、人間であるための必要条件です。
そして、人間であることは、動物であることの十分条件です。
次の有名なトルストイの言葉があります。
「幸せな家庭は皆同じだが、不幸な家庭はさまざまに不幸だ」
これを必要条件と十分条件で考えると、以下になります。
家庭が幸せになるための必要条件は、いくつもあります。
(例 経済的に恵まれていること、家族の仲が良いこと、家族が全員健康であること、など)
幸せな家庭になるにはこれらのすべてを満たす必要があります。
(金持ちでなくても幸せな家庭はありますし、これらすべての必要条件を満たす必要はあるか不明ですが、今回は省きます)
こういうそれぞれの必要条件を満たした家庭は、様々な点で同じなので、似たものとなります。
一方、必要条件の一つでも満たさないと、その家庭は不幸になるとも言えます。
(例 家族の仲が良く、経済的に恵まれていても、家族の誰かが病気になると、不幸。あるいは、経済的に恵まれていて全員健康でも、家族のメンバーで仲たがいあると不幸)
不幸な家庭にはいろいろな種類があります。
つまり、不幸になるための十分条件はたくさんあります。
(例 家族の誰かが病気であること、家屋の仲が悪いこと、経済的に恵まれていないこと など)
これらの条件の一つでも該当すれば、不幸な家庭です。
不幸な家庭はさまざまな理由で不幸になり、様々な類型があります。
では、「事業での失敗は簡単だが、成功は難しい」といえるでしょうか?
事業は数ある条件の一つでも満たさなければ失敗します。
一方、「事業に成功するのは、多数の条件をすべて満たさなければならないので、難しい」のでしょうか?
これは実は確率が関係しており、必ずしも正しくはありません。
無数の変数の確率の掛け合わせによって、成功する確率は変わります。
トルストイは「幸福な家庭は似ている」といっただけで、「数が少ない」とは言っておらず、彼の数学的判断は正確なのです。
ダイヤモンドが発言した「不幸な家庭は多いが、幸福な家庭は少ない」は言い過ぎであり、努力によって確率を上げることはできます。
さて、「ビジネスで成功する方法は?」という質問に答えるのも難しく、理由は成功するには多数の条件を満たさんければならないからです。
そして、その変数をすべて列挙するのは困難です。
一方、失敗の条件が一つでも成立すれば失敗します。
だから、失敗の例を示すのは簡単であり、「失敗分析本」がたくさん発売されています。
つまり、「失敗の十分条件は簡単に示せる。しかし、成功の十分条件を示すのはきわめて難しい。多くの場合、成功について示せるのは、必要条件だけだ」となります。
いわば、「ビジネスや国家経営について、「こうすれば失敗する」は言えるが、「こうすれば成功する」は、ほとんどの場合、マユツバだ」ということです。
失敗の分析本を読んでも、同じ失敗は回避できるかもしれませんが、成功できるとは限りませんし、ましてや失敗の研究書をよめば成功できると思うのは錯覚です。
勉強の場合は、ビジネスとは違い、変数が明らかで固定的なので、成功の十分条件を示すことができます。
野口悠紀雄氏の本は参考になるのでぜひ読んでみてください。
3 まとめ。
では最後にまとめておきます。
1 個人のIQと集団IQは異なるものであり、チームのパフォーマンス(集団IQ)を決めるのは個々の能力(IQ)ではなく、コミュ力だったことが判明しているとのこと。
また、今の時代、個人ではなくチームで活動することが多くなっており、そのチームの功績は「社会の捉え方」で決まる。
しかも「功績が認められるのは1人だけ」と述べられいる。
「手柄を横取りされたくなければ引用した本を読んでみてください」ということでした。
2 企業の事例の商売の成功法則は「製品・サービスの質+ブランドイメージ」が「拡散力」によって売れるか決まると僕は書いています。
詳しくは記事を読み返してください。
3 「強いとは資源をたくさん持っていること」である。
戦力が豊富にあるのが強者であるが、N国党の立花孝志さんは資源が限られた中で戦う弱者である。
そして、そんな弱者でも成果を挙げたのだから、創意工夫で戦力不足を補ったという意味で優秀だと僕は主張しました。
ではこの辺で。(3782文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。




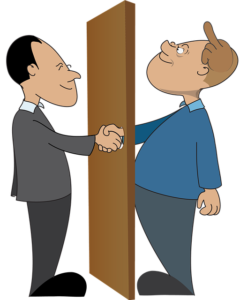



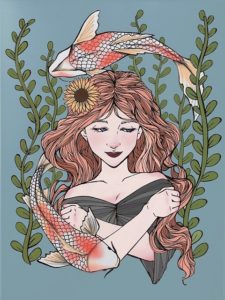

コメント