どうも、太陽です。(No11)
突然ですが、皆さんは売上が上がらなかったり、お客さんが集まらなくて悩んだ経験はありませんか?
「東大教授が教えるヤバイマーケティング」によると、ビジネスには物理学のように「絶対に成功する方法がない」と書かれています。
どうすればいいのか悩みますよね。。。
しかし別の本を読んだら、僕は商売で成功するための重大な要素に気が付いてしまいました。
今回はその重要な要素について、「皆さんに語ってみたい」と思います。
1 商売には絶対に成功する法則はないという理由。
いきなりですが、商売において物理学みたいな成功の法則を述べるのは非常に難しいことです。
さて、以下の本から引用します。
少し、難しいことを言っていますが、ぜひ読んでみてください。
企業の内部要因は、マーケティング、財務、研究・開発、製造、組織、人事などに分類できます。
そして、個々の分類の中にも多数の要因が存在します。
たとえば、マーケティングに関する要因の一部を挙げてみても、以下があります。
企業・製品・サービスの評判、マーケッ トシェア、顧客満足、顧客維持、製品・サービス品質、価格、流通、販促、広告、セ ールス・フォースなど。
また企業の外部要因は、以下に分類できます。
政治・法律、経済、文化、社会、技術などに関するマクロ的要素と、市場、顧客、競合、供給業者、流通業者などに関するミクロ的要素など。
これら無数の要因が存在し、それらの間に複雑な相互作用が起きた結果として業績が決まるのです。
たとえ企業の内部要因が過去とすべて同じであっても、競合会社の出方次第で成功したり失敗したりと、結果は大きく違ってくるでしょう。
よく、「ビジネスは物理学とは違う」という人がいますが、この比喩は適切ではないように思われます。
A4の紙を2階の窓から落として、どこに落ちるかを考えてみましょう。
紙の丸まり方(内部要因)は1枚1枚微妙に違いますし、温度や湿度(外部要因)で変わってきます。
その温度・湿度は、ミリ単位の場所と秒単位の時間で違います。
いつ、どこで、どこから、どの程度の風が吹くかも分かりません(外部要因)。
この例でも、無数の要因が落下位置に影響を与えるのです。
こう考えると、将来、 どれだけ科学理論やコンピュータの技術が進歩しても、「どこに落下するか」を予測することは不可能でしょう。
ビジネスの世界も同じです。
人は「永遠の命」という言葉に魅了され、時の権力者は「不死の薬」を探し続けました。
同様に経営者も、「永続する成功」の法則・原則を知りたがるのですが、それは、はかない妄想なのです。
ではビジネス書は無用かというと、そうではありません。
一番の役割、それは自己啓発ではないでしょうか。
「倫理観を持って、原理、原則に立ち戻り、精一杯努力すれば報われる」ことを、説得力のあるストーリーで分かりやすく教え、元気と勇気と 自信を与えてくれるのです。
P272、273。以上、ここまで。
ビジネス書に「永続する成功」の法則・原則なんて存在しないと書かれています。
僕もほぼ同感ですが、果たして本当に100%存在しないのでしょうか?
2 僕の考える成功・商売の法則。
僕の考える成功・商売の法則を述べますね。
それは以下の図式です。
企業の事例。
1 「製品・サービスの質+ブランドイメージ」が「拡散力」によって売れるか決まる です。
人間の事例。
2 「実力+人格(イメージ)」が「拡散力」によって出世したり、成功するか決まるです。
しかし、この事例は人間の事例の場合、主に1人のケースです。
で、企業の事例の場合、チームとなります。
(1人とチームでは成功・商売の法則は違うのです)
今回はわかりやすくするためにまとめて話していますが、あとで分けます。
詳しく説明していきますね。
商売の基本は「何を」(プロダクト)、「誰に」「どうやって」(マーケティング+ビジネスモデル) 売る になります。
「何を」の部分が企業で言えば、「製品・サービスの質+ブランドイメージ」なわけです。
質が高い、または魅力的な商品・サービスでも、ブランドイメージがあるかないかによっても売れるかどうかは左右されます。
ブランドイメージが高いと、想起されやすく、選ばれやすくなるのです。
で、ブランドイメージが地に落ちると、もはや売れなくなります。
(かんぽ生命は今後、危険水域でしょう)
また「誰に」「どうやって」売るかは「拡散力」であり、マーケティングです。
で、「メディアでの宣伝やビジネスモデルなどによって他社と差別化し、販促する」ということになります。
4Pというマーケティング用語がありますが、「Price」(価格)、「Product」(製品)、「Place」(流通)、「Promotion」(販促)ということになり、前者2つは「何を」の部分であり、後者2つは「誰に」「どうやって」売るの部分になります。
要はいくら良い商品でも、知られなければ売れないということです。
これを人間の出世や成功に同じく当てはめてみましょう。
(1人の人間の事例です)
「実力+人格(イメージ」は「何を」の部分です。
で、「拡散力」とはその人自身の「実力+人格(イメージ)」が「広く大衆に」か、または「実力者などに知れ渡ること」を指します。
実力がある人がいても、拡散されなければ知られなければ成功しないのです。
また、実力があっても週刊誌などにより、人格面を攻撃され、イメージに傷がつくと、人気商売の場合は売れなくなるかもしれません。
(人気商売じゃなければダメージは少ないです。役立つ知識・情報を売るDラボのメンタリストDaiGoはおそらく大丈夫でしょう)
実力がある人はメディアなどにより拡散されることで、ブランドイメージもつき、知名度が上がり、売れやすくなります。
しかし、ここで注意点があります。
実力というのはそもそも、上位層になるとかなり拮抗しているという点です。
僅差なのです。
圧倒的な差というのはそう簡単にはつきません。
よって、実力者(上位層)といっても、その背後には追随者が大勢います。
で、あとは「人格や拡散力など」によって、売れるか決まるということなのです。
ですが、この話はあくまで上位の実力者(上位層)を指すものです。
中級者ぐらいになると、いくら拡散しても長期的に見たら、売れないのです。
いい例が、一発屋であり、ピコ太郎などは典型例でしょう。
まがいものはいくら事務所などがゴリ押ししても、そのうちに飽きられます。
中級者・下位者になると、まがいものですから、長期的には成功しません。
また、本当の実力者は拡散力が弱くても、地道にのし上がることも可能なようです。
やはり、見る人が見たら本物とわかるわけです。
そして、宣伝力が弱くても長く続けていけば少しずつ、知られていく可能性もあるのです。
そしてこういう人は一度、拡散されたら一気にブレイクする可能性が高いです。
3 商売の具体例。
商売の具体例を見ていきましょう。
「ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした「成功の普遍的法則」という本のP190〜を引用・まとめしてみます。
(僕の解釈付きです)
人の好みは周囲の影響を受けやすいですが、目の前の製品がお粗末だったら気づきます。
(いくらゴリ押しで、皆がいいと思うように誘導・拡散されても、中級や下位レベルの製品なら、長期的には売れないということ)
ですが、製品の質には上限があります。
そして、そこそこの選択肢を目の前に並べられると、自分の判断を曲げて「周囲の意見」に従ってしまいます。
(実力者・上位層は拮抗しており、その中で選ぶとしたら「拡散されている・有名・人気がある方」を選ぶということです)
「人気のある製品」が必ずしも本当に優れているとは限りません。
また、人々が本当に欲しているのは顧客のニーズを満たすものであり、単に「世間で人気な製品」ではないのです。
(人は「拡散されている、有名・人気な方」を選びがちです。ですが、それは拡散力によって人気を得たかもしれません。または「本当に顧客が欲しくて買ったか?」は不明ということです)
人が製品やサービスの購入を判断するのは「人気」と「その製品の真価」の2択なら、以下の理由で選んでしまいがちです。
つまり、その分野での目利きじゃない限り、「その製品の真価」まで判断できず、「人気」によって選ぶのです。
だから、そこそこの実力者・上位層で成功するのは拡散力次第ということになるのです。
または一度、人気がでたら、加速し、一人勝ちになります。
もちろんその加速も停滞することはあり得ますが。
「本物や本当の実力者」が必ずしも成功しているわけじゃないのですね。
メディアでのプッシュ(拡散力)がかなり影響するのです。
娯楽の本や低俗なテレビ番組を見るのなら、「人気」や「話題」というだけで選んで見てもかまわないでしょう。
ですが、大学や医師や選挙の候補者を選ぶ際は「世間で人気だから」で選ぶと痛い目に遭います。
人生を左右するようなモノを選ぶ際は「世間での人気や知名度」に左右されず、「本物」を選ぶようにしたいものです。
4 実力の意味。
また、ここで「実力」というモノについて述べていきます。
実力というのは「上位層は僅差だ」と述べました。
例えば、ある大会(コンクール)で一度優勝すると、その人は引き上げられやすくなり、そこから成功へのループ(連鎖)が始まるのです。
大会出場者で、最終選考に残る人は全員が才能には恵まれています。
ですが、ほとんど優劣が判断できず、最終的には「運」と「バイアス」によって差がつき、その後、ずっと成功し、生き延びるかが決まってしまうのです。
「成功が成功を生む」という現象ですね。
(もちろん、その成功もずっと続くとは限りません)
また、どんなスーパースターでもパフォーマンスには上限があり、ライバルとも僅差の実力差なのです。
スーパースター教授の例なども本には詳しく載っているのでぜひお読みください。
PART2の記事へ続きます。

ではこの辺で。(4256文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを基にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。




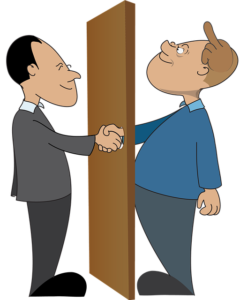



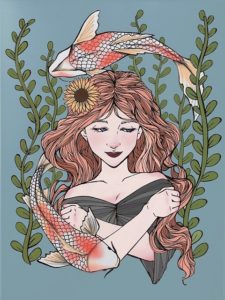

コメント