どうも、太陽です。(No1)
突然ですが、僕は起業していませんが、過去に最低5000冊以上のビジネス書を読破しています。
その知見から「起業を目指している人へ何かアドバイスができないか?」考えてみたという話が今回の記事です。
「起業相談に無料で乗ってみた」という体裁にしました。
興味がある人は続きをお読み下さい。
1 起業相談の内容。
いきなりですが、起業相談の内容は以下のものでした。
「大目標は決まっていますが、具体的に何をしたら良いのか分かりません。どうしたらいいですか?」
つまり、大雑把なやりたいことは決まっているのですが、「そのための具体策がイマイチ浮かんでいない」ということです。
だからこそ「日々の行動に落とし込んで実践できていない」という悩みです。
こういうぼんやりした「なんでもいいから起業したい!」「やりたいことがある!」「ビジネスをしたい!」という野望を持っている人は「少なからずいる」と思います。
今回はそういう方へ向けて、僕がアドバイスします。
まず、「受験勉強とビジネスは違う」という話をします。
受験は決まった目標(大学合格)があり、過去問があります。
そのためのやるべき参考書などがある程度は決まっているからこそ、受験日から逆算して、やるべきことを日々着実に積み重ねていけば合格できます。
しかし、ビジネスにおいては大雑把な目標があっても、過去問はありません。
(リサーチして前例があるか調べるのは重要)
やるべき定番の参考書もなく、逆算思考で日々のやるべきことをリストアップしづらいのです。
僕の考えとして、やるべきことがあるのなら、以下のことをすればいいとなります。
それに必要なスキル・資金・人材・プロダクトなどを洗い出し、着実にそれらを磨いたり、集めればいいのです。
4Pというマーケティング用語があります。
以下の頭文字をとったものです。
| ・ | Product(製品・商品) |
| ・ | Price(価格) |
| ・ | Promotion(プロモーション) |
| ・ | Place(流通) |
つまり、何を(どのような商品をいくらで)、どのように届けるか(宣伝と流通)の一連の流れのことです。
また、イノベーター理論という概念もあります。
以下の順に、商品が売れていくのです。
| 1 | イノベーター。(2.5%) | マニアがまず飛びつく。 |
| 2 | アーリーアダプター。(13.5%) | ミーハーが飛びつく。 |
| ここで、キャズム(深い溝)があります 。 これを超えないと、一般層に広がりません。 | ||
| 3 | アーリーマジョリティ。(34%) | 大衆に浸透する。 |
| 4 | レイトマジョリティ。(34%) | 無関心層にも浸透する。 |
| 5 | ラガード。(16%) | 携帯でいえば、いつまでもガラケーを使っている人達。 |
PLC(プロダクトライフサイクル)というマーケティング用語もあります。
以下の4つの製品・市場の成長パターンがあります。
| ・ | 導入期。(ビジネスの初期) |
| ・ | 成長期。(売上高が急成長) |
| ・ | 成熟期。(売上高が安定) |
| ・ | 衰退期。(売上高が減少し始める。製品・市場の寿命) |
「自分のビジネスがどの時期にあるか?」を見極める必要があります。
PEST分析もあります。
以下の4つの「自分のビジネスに影響を与える外部環境」を把握しておく必要があります。
| ・ | Politics(政治) | 法改正(規制・緩和)、税制(減税・増税)、政権交代など。 |
| ・ | Economy(経済) | 景気動向、物価、消費動向、為替・株価・金利・原油など。 |
| ・ | Society(社会) | 人口動態、流行・世論、宗教・教育・言語など。 |
| ・ | Technology(技術) | インフラ、IT活用、イノベーション、技術開発、特許など。 |
以上は「何を売るべきか?製品やサービスが明確化している前提での武器となる情報」でした。
ですが、「そもそもやるべき目標・戦略が有効か?」の吟味も必要です。
3C分析により、事業を客観視します。
| ・ | Company。(自社) | 自社はどうなっているか? (強みなど多数) |
| ・ | Compititor。(競合) | ライバルはどうなっているか。 |
| ・ | Costomer。(市場) | 市場や顧客はどうなっているか。 |
そもそも、コア・コンピタンス(競合他社に真似できない核となる能力)がないと、すぐに他社に真似されて、追い抜かれます。
一番乗り(先行者利益)で有利になる場合もあります。
ですが、それよりも後発組(2番手など)が勝つケースも多いのです。
(Facebookは典型例)
また、コトラーの競争地位戦略という概念もあります。
以下の立場・地位の戦略をそれぞれが採ります。
| ・ | リーダー。 | 一番手企業。全方位方針。 |
| ・ | チャレンジャー。 | 二・三番手企業。差別化。 |
| ・ | フォロワー。 | 二・三番手企業。模倣。 |
| ・ | ニッチャー。 | 弱者の戦略。隙間市場を狙う。集中と選択。 |
弱者の戦略は良い面がかなりあります。
| ・ | 大企業が参入しても儲からないので、攻めてこない。 |
| ・ | マニアックな顧客を狙うので、市場や売上は小さいが、根強い人気が得られる。 (ライバルも少ない) |
| ・ | 自社が限りある経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)を絞り込んで投入できる。 |
まさに弱者こそ採るべき戦略・立ち位置となります。
または、ブルーオーシャン戦略(レッドオーシャン(血の海)じゃなく、ライバルがいない青い海で戦う)や、孫氏の兵法の「戦わずして勝つ」も、最良の方法なのです。
以下の本で詳しい内容が書かれています。
「競争しない競争戦略 改訂版 環境激変下で生き残る3つの選択」
個人が起業したいのであれば、まずは「コア・コンピタンス(真似されない圧倒的な強み)を構築すべきだ」と僕は思います。
強みを見つけたい人は以下の本が参考になります。
「さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0」
<注意> 本を買うと、強みのテストを受けられますが新刊じゃないとダメです。
コア・コンピタンスなしに、人脈をむやみやたらに広げて外注しまくる人もいます。
ですが、人がついてくるか微妙なところです。
「人を動かす」の著書で有名な、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの名言「おのれよりも優れた者に働いてもらう方法を知る男ここに眠る」があります。
よほどの人望や人間力がある人なら別かもしれませんが、普通は何も能力がない人に人はついてこないものです。
(もしくは会社なら、追放される可能性があります)
また、プログラミングなどの外注でも、価格相場に詳しくないとぼったくられます。
(もちろん、相場価格に詳しい人を味方につければOKですが)
「圧倒的な強みを構築し、わらしべ長者戦略により、徐々に人脈を拡大していくのが無難なのかな」と思います。
「人は自分と同じレベルの人としかつるまない」というように、能力がないと思われたら、仲間になってくれないのです。
ですから、核となる自分の強みを構築し、会社を作っても「自分がいないと回らないようにすべき」です。
(会社の規模が大きくなったら、自分がいなくても回るようにする)
少なくとも追放されたり、裏切られるリスクは減らしましょう。
あとは、徐々に自分が仲間となれる相手をレベルアップしていく、わらしべ長者戦略がお勧めです。
「人は自分と同じレベルの人としかつるまない」法則があります。
自分の実力が低いうちは自分より少し上の人と付き合い、全てを吸収しましょう。
もちろん最低限の心遣いや労力などのGiVE&TAKEをしつつ、付き合う相手をレベルアップしていくのです。
加えて、強みは組み合わせるのが大事です。
強みが1つで90点以上のスペシャリストは険しい道のりです。
ですが、70点ぐらいを3つ組み合わせるのは前者に比べたら楽です。
組み合わせかたによっても、個性が出てきます。
また、本で「基礎的な知識を網羅的に吸収しておくこと」はかなりお勧めです。
試験でも、80点から90点・100点にするのはかなりの労力が必要です。
ですが、0点から50点にするのは比較的、楽であり、費用対効果が高いのです。
「かなり幅広いジャンルで30点〜50点ぐらいの土台を作りつつ、70点ぐらいの強みを3つつくる」のがやりやすい道です。
僕のブログでは基礎的な本を大量に紹介しますので、多読により、基礎力をつけてください。
そうやって、まずは読書などにより、自力で強みを作った方が、人脈作りにおいても良い人とつながれます。
魅力も乏しく、武器もない人が人脈を作るのはお勧めしません。
(長期的に相手にされません)
ここで注意点があり、強み構築も大事なのですが、「ニーズに合った強みかどうか?」という視点があります。
以下の用語があります。
| ・ | プロダクト・アウト。 | (作ったものを売る) |
| ・ | マーケット・イン。 | (売れるものを作る) |
プロダクト・アウトは自社の資源目線であり、作れるモノから発想します。
マーケット・インは顧客目線(ニーズ)です。
自社で足りない資源は他社と協働や提携や外注、さらにはM&Aしたりして、売れるモノを作ります。
マーケット・インを重視しないと、いくら強みであろうが、売れません。
政治学や社会学などを勉強して、組み合わせてもニーズが乏しく、ビジネスにしづらい上に刺さりません。
(「強み構築の際はニーズも大事にしましょう!」という主張です)
また、起業当初は予算が限られていますから、なるべく自分が積極的に広告塔になりましょう。
(ブログ・YouTubeなど。孫正義さんも広告塔効果で、CM予算を減らせましたね)
以上、簡単な仮想の起業相談でした。
参考になる方がいれば幸いです。
また、「戦略って弱者のためのものだ」と感じます。
3C分析(自社、競合、顧客・市場)って、強者ならそこまで考える必要がありません。
かなりの強者は能力をそこまで考える必要がなく、ライバルもほとんど蹴散らせる上に、顧客・市場のニーズも致命的に間違っていなければ満たせるのかなと。
さらに、4P(価格、Product、Promotion、Place)に関しても、強者なら、1人勝ちなので値付けし放題、プロダクトもある程度作れて、宣伝も有名人なら簡単です。
弱者は「何ができるか?」をかなり考え、ライバルをかなり気にし、顧客・市場、ニーズを相当、研究しないとたどり着きません。
また、価格付けも不利で、プロダクトもイマイチ、宣伝もかけられません。
「TVに出れる、有名人」というだけで宣伝はクリアです。
なんの知名度もない一般人がYouTubeやブログでのし上がるのはかなりの困難な道です。
弱者ほど、資源・リソースがほとんどないので、戦略が必要です。
また、以下の「考える力」は今の時代に身につけると、強力な武器になるでしょう。

これからの時代に必須な「考える力」を身につける5つの方法
最後に、以下の本は起業するにせよ、サラリーマンにせよ、社会人として最低限必要なビジネス用語が学べる良書です。
これくらいは身につけておきたいです。
ではこの辺で。(3937文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。




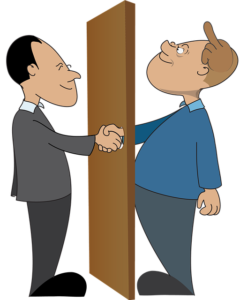



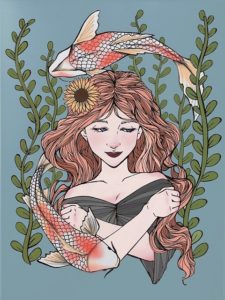

コメント