どうも、太陽です。(No22)
突然ですが、今回の記事は以下の本を参考にしています。
日本は「過剰サービスが多い」と僕は感じています。
その日本の過剰サービスは住むには素晴らしいですが、働く側にとってはかなりの負担になります。
その日本の過剰サービスについて、画期的な改善策を述べます。
興味がある人は、続きをお読みください。
1 本からのクイズ問題。
まず、以下の本に書いてあったクイズ問題を書きます。
この本で、「レンタルサービス会社の問題」について述べられていました。
レンタルとはビデオのことを指します。
ビデオの巻き戻しをしないで返却する層がけっこういて、それに不満を覚える層が40%ぐらいいたという話です。
この問題を「アメとムチのインセンティブ(罰金や報奨金など)もなしに、金銭もほぼかけずに解決するにはどうしたらいいか?」という問題でした。
考えてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
答えを述べます。
答えは、「そもそも、巻き戻しをしないで返却してもOK」というシステムにすることです。
そうなれば、「巻き戻しをされていない」が標準になるので、不満を覚えることもなくなるのです。
本にはこのような答えが書いてあったと思います。(確か)
2 日本の過剰サービス業の改善策
この発想を元に、日本の過剰なサービス業を改善することを考えます。
コンビニやスーパーなどで、椅子に座らずに立って接客をしていますが、椅子に座るのを当たり前にすれば誰も不満を感じなくなるでしょう。
地方では、椅子に座っている定員を見かけます。
座って接客されると、「頑張ってない」と今ではみなされがちだと思いますが、これは今が標準なだけであり、座るのが当たり前になれば「不満など感じなくなる」と思います
この他にも、「過剰なサービス活動はある」と思います。
例えば、アメリカや日本では「笑顔で接客が当たり前」ですが、フランスでは笑顔を見せるかどうかは個人の裁量に任されているのです。
面白くもないのに、ニコニコしなければならないストレスとは無縁な国がフランスです。
こういうのを過剰にやらないのを当たり前にすればいいのです。
日本のサービス業は「過剰なサービスにより、生産性を下げている」と言われています。
1人につき、負担が高くなっている上に、儲けが少なくなっているからですね。
日本の過剰なサービス業は、改善の余地があるかもしれません。
そもそも、時給800円くらいの仕事に、そこまでのサービスを求める方が酷じゃないですかね?
時給1500円ぐらいいくなら、過剰サービスもありかもしれませんが。
安い時給で、過剰サービスは「やはり酷だ」と思うのです。
日本政府が音頭を取って、標準化しないと「過剰サービスだいう問題意識すらなくならない」と思います。
企業はどこも競争しており、過剰サービス合戦になりがちだからです。
標準化してしまえば当たり前になり、不満を持たなくなると思います。
そのためにやることは政府が音頭を取って制度化するだけです。
コストもほぼかかりません。
消費者は多少、不便になりますけどね。
3 僕の改善策とほぼ同じ意見。
さて、以下の記事を貼ります。
https://news.yahoo.co.jp/byline/nakaharakeisuke/20191125-00152305/
「日本の生産性が低いのは、日本人の価値観の問題だ」というタイトルです。
2019年11月25日の投稿ですね。
一部を引用します。
日本の低生産性の主因であるサービス業でも、業界によっては生産性を確実に引き上げる方法があります。
たとえば運輸業のなかでも成長が著しい宅配便事業では、アメリカと同じように、荷物を玄関前などに置いて届ける「置き配」という手法が一般的になれば、業界全体の生産性を容易に1割程度は上げることができます。
業界の統計によれば、宅配便が再配達になる割合は2割程度とされているので、宅配便に特化する事業者であれば、その生産性を2割程度上げることに直結するのです。
日本人がアメリカ人の受けているサービス水準と同じで構わないと思うことができれば、宅配便業者の生産性は2割程度も上がるばかりか、働く人々の給与アップやモチベーションの向上にもつながります。
それに加えて、業界の深刻な人手不足を大いに緩和することもできます。
当然のことながら、置き配を認めない消費者向けには、宅配便ボックスの設置を要請したり、料金の上乗せをお願いしたり、コンビニ受け取りを勧めたりする取り組みも欠かせないでしょう。以上、ここまで。
置き配という解決策は、ほぼ手軽にできる過剰サービス改善策ですね。
問題は、「窃盗されたらどうするんだ!」ということだけですかね。
今や、「置き配」は普通に利用され、普及しています。
ではこの辺で。(2131文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。
「すごい心理学」




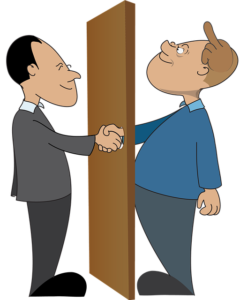



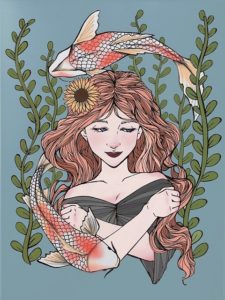

コメント