どうも、太陽です。(No48)
 悩み人
悩み人「日本の労働生産性は低い!」とかなり喧伝されているよね?
2020年の調査では、労働生産性はOECD加盟37カ国中21位、G7(先進7カ国)では最下位となっている。
しかし、別のデータから見ると、そうでもないことが分かります。
このことについて詳しく考察していくので興味がある人は続きを読んでください。
(異論は認めます)
1 G7の中では正社員に絞ると労働生産性がトップクラスというデータ。
知り合いによると、G7の中では「正社員に絞ると労働生産性がトップクラス」というデータを竹中平蔵の本で見かけたと言っています。
この主張を元に、論理を組み立てていきます。
また、以下のシータさんのツイートもこの主張を強化します。


つまり、GDPを生産年齢人口で割ると、日本はトップなのです。
要は非正規を入れても労働者全体でみて、日本の労働生産性はトップです。
「正社員でもトップ、非正規を入れてもトップ」ということは、単に日本には悪い言い方をすれば「お荷物となる高齢者が多すぎる」というだけという話になります。



えー、そうなの?
日本の労働者はG7の他国と比べても相当に現時点でも頑張っており、逆にいえば伸びしろがないと言えます。
(「最大限に頑張っているのに、これ以上に頑張らせるのか?」という話です)
しかし、高齢化率も世界で断トツでトップで、高齢者が多い日本では政治的に彼らを無視できません。
よって、高齢者優遇の年金・医療・介護費大判振る舞いの政治をしています。



日本はG7トップクラスの労働生産性の労働者が「大量の高齢者を養っている国」ってことか。
そうです。
しかも、60代以上の高齢者の数は3割程度なのに、持っている資産の割合は全体の70%以上という歪な構造になっています。
(少数の高齢者に資産が集中しています)
しかし、高齢者優遇は数の論理から言って、大幅に路線変更をすることは政治的に困難です。
ですので、「年金額を毎年少しずつ減らす」という対処療法を20年以上持続という、ゆでガエル状態を続けるしかありません。



ということは、「ただでさえ筋肉質な労働者の生産性をさらに高める」という無茶を日本はやらないといけないのかぁ。
はい。
日本の失われた30年のうち、約15年ぐらいの主因は高齢者の負担が多すぎたことだったのです。
(つまり、急激に高齢化率が高まったのが約15年ぐらいと見ます。加えて、イノベーション的製品を高齢者は金をたくさん持っているのに使いこなせないから買いません)
高齢化の定義は、65歳以上人口の割合が7%超で「高齢化社会」、14%超で「高齢社会」、21%超では「超高齢化社会」と呼ばれます。
日本は2008年には「超高齢国家」です。
つまり、2022年から巻き戻すと、14年前にはすでに「超高齢国家」ということになり、約15年くらいの期間、「高齢化率が急激に高まった」という僕の主張とほぼ似通っています。



しかも2位以下の諸国を大幅に引き離して、断トツ1位のほぼ3割の高齢化率だよね。
そうです。
だけど、1980年代までは高齢化率は10%以下で、むしろ米国や欧州諸国に比べて「高齢者の少ない国だった」ので、1990年代から急激に高齢化率が上がったことが分かります。
さて、労働者はせっせと高齢者の年金・医療・介護のために、保険料などを払っています。
(「税金をかなり多く取られている」と実感しているサラリーマンは多いのでしょう)
2 世界トップの労働者の生産性をさらに上げるにはどうすればいいか?
無茶苦茶ですが、世界トップの労働者の生産性をさらに上げないと日本は成長しません。
(もしくは合法的に高齢者から金を奪い取る、つまり高齢者に大量に消費してもらい、労働者に金を移転させるなどです。維新の会の提唱する資産課税などの人権侵害の強硬手段ではなく、消費という手段により金を移動させます)



日本では製造業の賃金は高く、輸出主導型経済の路線のままで行くのだとしたら、ドイツに学ぶ道もありそうだけど、ドイツのお国柄を考えると相当に真似をするのは厳しそう。
はい。
ドイツは経営者にも厳しく、労働者にも厳しい国であり、切磋琢磨して質の高い製品を作っていますから。
一方、日本では経営困難の企業を税金で延命させたり、不正会計が発覚しても経営者がペナルティを課されないなど、大企業の経営者に甘いです。
しかも、150円の円安により、下駄を履かせてもらった輸出企業、特にトヨタは大儲けです。
(努力しなくても、生産性を上げなくても利益が上がるので、モチベーションが湧きません)
そして、中小企業の経営者に対しては、株式会社なのに事実上の無限責任を課すなど矛盾しています。
2020年版の中小企業白書によると、2017年の日本の廃業率は約3.5%だったのですが、ドイツは7.6%と約2倍です。
ドイツでは企業の新陳代謝(廃業と創業)が活発なのです。
労働者に対して厳しい措置として、解雇規制の緩和や社会保障費の削減があります。
で、経営者に厳しい措置といえば、コーポレートガバナンスの強化や馴れ合い経営の排除といったものになります。
日本では労働者に厳しい政策がとられがちです。
(非正規雇用など)
一方、ドイツでは労働者にも厳しいですが、経営者にも厳しく、利益を上げられない経営者は存在価値がないとみなされます。
ドイツの製造業を真似るのは並大抵ではありません。
EU市場とアメリカ市場というお客様がいて、交渉力があるドイツと、アメリカ市場にべったりで、今後、中国に追従しなくてはいけなくなる日本では状況・立場が違うので、ドイツを後追いしなくていいのです。
(しかも、EVシフトを日本の自動車業界はしなくてはいけないかもしれません。原発をどれだけ作ればいいか不明なほどです)
さて、以下の記事で、日本は「インフレ・円安に適応した国にならないといけない」と述べました。


超円安でiPhoneが高すぎて買えない日がくる「円安円高どっちがいいのか論」
「縮小ニッポンの再興戦略」という本で、アメリカや将来の中国のような「消費主導型経済に構造転換すべきだ!」が日本の針路だと書かれていました。
僕の見立て「インフレ・円安時代」、つまり、「輸出主導と消費市場のハイブリッドを続けるしかない」という立場とは異なっています。



円高に政策変更でできるなら、著者の主張もありえるだろうけど、現実的に円高路線にできるのかな?
ここで著者の主張を見ていきます。
(僕個人の主張も混ぜます)
GDPの中で個人消費が占める割合は、米国(約68%)、日本(約55%)、ドイツ(約50%)です。
そして、日本は米国(消費主導型)とドイツ(輸出主導型)の中間に位置します。
日本が他国と比べて低成長なのは、消費低迷が主因と主張しています。
通貨安がメリットになるかデメリットになるかの指標の一つとして交易条件がありますが、日本の交易条件は一時期を除いてずっと悪化しています。
(つまり、円安は害です)
円安を防ぐには、消費を活発化させるしかありませんが、日本は以下の人が消費するメカニズムに合致しており、消費を活性化するのは厳しそうです。
(ちなみに、経済学では消費を拡大化する絶対的な方法は解明されていません)
| 1 | 恒常所得仮説。 | 人々は、一時的な所得の増減(変動所得)ではなく、将来予想される所得の平均的な水準(恒常所得)を基準に消費を決める。 これまで獲得してきた賃金水準の推移や、自身が持つスキルなど過去の成果を基準に、合理的に将来の賃金を予想する考え。 |
| 2 | ライフサイクル仮説。 | 人々は人生設計を通じて生涯所得(一生涯の間に獲得できる所得)を推定し、それを基準に現在の消費を決定する理論。 生涯で獲得できる所得の総額を基準にして現在の消費を決める考え。 |
| 3 | ケインズの消費理論。 | 所得の一定割合を消費に回す。 |



恒常所得仮説もライフサイクル仮説も、将来の所得によって今の消費を決めるという点で同じだね。
そうです。
つまり、現在の日本の状況、賃金が連続的に上向く気配がなく、年金財政は徐々に悪化するのが見えているとしたら、将来の所得や貯金が減るのは分かりきったことです。
だとしたら「現在の消費を減らす」というのは合理的な行動です。
一時的な政府による企業への賃上げ要請や、10万円の給付金程度では、国民の将来不安は払拭できません。
将来の見通しを明るくしない限り、日本人が「今後も消費を活発化させる可能性は低い」と思われます。
つまり、抜本的な年金・医療・介護改革をして老後の不安を消すことや、少子化を食い止め、人口も着実に増え、賃金も毎年上がるなど、明るい未来予想図を描かないといけません。
不安遺伝子が特に多い日本人は財布のヒモを固くしめたままになる恐れが非常に高いのです。



あと、トップクラスの労働生産性を誇る日本の労働者に対し、さらなる試練を与えるとしたら、解雇規制の緩和になるね。
はい。
日本は解雇規制を緩和しないことにより、つまりクビにしづらいことで、正社員採用へのハードルが高くなり、それで非正規雇用を増やし、企業はコスト削減を図ってきました。
失業率は下がりましたが、熾烈な競争はなく、個人は鍛えられませんでした。
そして、転職市場も整備されていないので、ぬるま湯状態で同じ会社に正社員、非正規が同じ仕事をして、居続ける構造です。
(非正規の給料は正社員の3分の2程度です)





つまり、企業は売上高を上げるよりも、コスト削減に走った。
で、精鋭部隊の正社員、非正規という構図で長年、しのいできたってことね。
はい。
過去10年売上高は増えておらず、つまり企業業績は拡大していないのにもかかわらず、営業利益はある程度伸びました。
その理由は、非正規の増加や若年層の賃金引き下げによるコストダウンでした。
また、営業利益率と純利益率に大差がなく、つまり、法人税減税によって企業はゲタを履かせてもらって企業経営をしています。
加えて、大企業経営者は怠けて、利益を追求せず、内部留保ばかり溜め込み、さらにオフィスビルを立て直すというマズイ行動をとっています。
(詳しい理由は本で)
話を戻します。
労働者をさらに鍛えるには、解雇規制の緩和なのですが、失業率が上がると、政治家にとって失点になるので、採用しません。



つまり、外国のように「失業率は上がっても競争させて労働生産性や賃金を上げるか」、もしくは日本のように「失業率を下げて、解雇規制の緩和もせず、過酷な競争はさせず、賃金を上げないか」という選択になるのかぁ。
はい。
日本は失業率をとにかく上げたくありません。
同じ仕事をしている正規・非正規がいて、給料に差があり、非正規の分だけコストダウンして、売上拡大・成長していない分を補っています。
3 日本の将来の国家像とは?
話を戻します。
著者の消費主導型経済を確立するためには、消費低迷の原因となる将来不安を払拭することが第一ですが、それの実現がかなり難しいです。



生産性向上のカギとなるIT投資は、ハイブリッドにせよ、消費主導型にせよ、強化しなければならないね。
さて、以下の記事で書いたように、成長牽引型の産業を育成することも重要でしょう。


日本の賃金が上がらない理由。
加えて、日本の人口は少子化がこのまま大幅に改善しないとすれば、今の約1億2600万人から、8000万人レベルまで落ちるかもしれません。



「8000万人レベルに最悪、人口が減る」と想定しておくと、ドイツか韓国のような輸出主導型(輸出依存度が高くなる)の国家像を目指すしかないね。
(内需が弱くなるから)
はい。
仮に、移民を50万人〜100万人レベルで今後、受け入れ、2000万人増やし、元々の日本人8000万人+移民の2000万人の「1億人国家を目指す方向もありだ」と思います。
また、内需が弱くなるので、日本語に特化した産業は打撃をかなり受けます。
(執筆業、日本文化・芸術系、アフィリエイター・士業など、日本語で母国の日本人向けに商売していた人が困ります)



どちらにせよ、消費主導型は人口が大幅に減ることを考えると、将来的には厳しいね。
はい。
アメリカで消費主導型が確立しているのは「移民が持続的に流入しているのと、日本人のように不安型が少なく、将来への不安感も少ないから、消費が活発化しているのだ」と思われます。
また、安いニッポンが確立すると、将来的には東南アジアやフィリピンなどの国からも、外国人労働者が出稼ぎに来なくなる可能性が高いです。
(将来的にはそのような国も日本に追いつく可能性があります)
中・長期的には、円高+消費主導型経済を日本が確立するのは並大抵ではなく、消去法から「円安+ハイブリッド型にならざるを得ないのだ」と僕は考えています。
(ただし、「円安誘導のアベノミクスは時期が早すぎた」という可能性もあります。人口8000万レベルの国家なら、輸出主導の円安+ハイブリット型ですから)
生産性については以下の記事も参考になるかと。
https://toyokeizai.net/articles/-/629479?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=auto3h
誤解が多すぎ「日本の賃金が上がらない」真の理由
「短期的な賃金上昇策→物価上昇の好循環」の罠
この記事が皆さんの何かの気づきやヒントになれば幸いです。
では、この辺で。(5328文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。
https://news.yahoo.co.jp/byline/arakawakazuhisa/20220805-00308829
「高齢者よりも独身者の方が多く、若い独身より中年以上の独身が多い」~中高年ソロ国家ニッポン





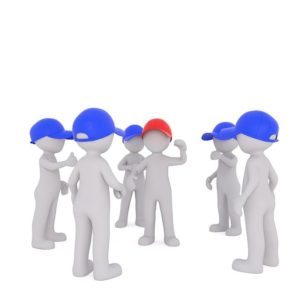




コメント