どうも、太陽です。(No54)
突然ですが、日本でGAFAが生まれない理由として、以下が挙げられています。
「国民性」や「起業家精神が足りない」や「教育のせい」や「高齢者が多く、イノベーティブな商品が売れない」などです。
そういう理由もあるでしょうが、今回の記事ではもっと根本的な原因を追求します。
ちなみにGAFAとは、Google、Amazon、Facebook(現メタ)、Apple4社の頭文字をとったものです。
また、為末大さんが以下のツイートで、「なぜ日本でスティーブ・ジョブズが生まれないのか?」について書いています。
簡単にいえば、アテンション(世間での注目)が足りないという主張です。
日本から大谷選手が生まれるのは野球が日本国民に認められていて、選手の層が厚いからであり、対して、日本の起業家の地位・人気は低いというわけです。
確かに、日本ではアメリカほど起業家人気が高くありません。(それはメディアが起業家を取り上げませんし、逆に、IT企業はTV局の敵であり、潰したい動機もあります)
まぁこういう主張も多少は関係していそうですが、もっと構造的な内容を今回の記事では取り上げます。
このテーマに興味がある人は続きをお読みください。
1 日本でGAFAが生まれない理由。
日本でGAFAが生まれない理由を考察します。
「メタバースがGAFA帝国の世界支配を破壊する!」という本をかなり参考にしました。
著者は深田萌絵さんです。
GAFAというか、日本から巨大なグローバルなSNSが出てこない理由として、以下があります。
SNSがデータセンタービジネスという巨大なインフラを必要とする産業という点です。
SNSは日本では昔はmixi、今はニコニコ動画でほそぼそとやっています。
で、ニコニコ動画はオタクにうまく課金できたから、サーバー代を賄えて事業を継続できているのです。
ちなみに、mixiが衰退した理由として、グローバル対応をしなかったことと、Facebookにもっていかれた、が挙げられます。
GAFAレベルになると、データセンターはもはや巨大な街です。
東京ドームのような土地にビルを建て、ビルの中にサーバーを大量に置き、自家発電機も備え、従業員が寝泊まりする場所、食事をする場所になっているのです。
巨大なSNSを作ろうと思えば、アマゾンのAWSに依存するのはダメで、自社サーバーを構築する必要があります。
さて、メンタリストDaiGoはAWSで、知識のNetflixであるDラボを運営していて、「サーバー代はそこまでかからない」と言っていました。
対して、TwitterもYouTubeアカウントもバンされた暴露系YouTuberで国会議員のガーシーは以下のことをしています。
封じられた言論の自由を構築するために、自前でサーバーを立て、オンラインサロンを作りました。
そして、サーバー代を賄うために、約4万人の有料会員から、月額3980円もとっているのです。
(今は円では受け取っていないようです)
AWSはある程度、費用を抑えることができる一方で、自前サーバーだと、サーバー構築・維持費や人件費など、けっこうかかるのです。
ところで、日本でガーシーがYouTubeやTwitterをバンされたことで、「日本に言論の自由がなかった」と身近に感じた人も一部にはいたでしょう。
ですが、実はアメリカでは既に前例がありました。
アメリカにおいて、2020年の大統領選挙後の10月、11月頃からFacebookやTwitterで言論統制を受けていた米保守派のユーザーがバーラーというSNSに移行しました。
そして、1500万人近くのユーザー数に達していました。
しかし、2021年1月6日に起きた米国会議事堂デモ事件でトランプ大統領支持者が暴動を煽った事件がありました。
で、米保守派が集まっていたバーラーはGoogleとAppleのアプリから、規約を守らなかったことで(言論の自由でバーラーは抵抗した)、締め出されました。
バーラーは2021年1月6日に「今後2年かけてインドから500億円〜700億円の資金調達を行い、自社のデータセンターを構築する」と発表しましたが、時すでに遅し。
アマゾンのAWSでバーラーは活動していましたが、AWSからも2021年1月10日に締め出されてしまいました。
さて、トランプ元大統領は米国会議事堂デモ事件がきっかけで、Twitter、Google、Appleから締めだされてしまいました。
ですが、トランプ元大統領の独自SNS「トゥルース・ソーシャル」が2022年2月にAppleStoreからリリースされました。
そして、順調に行くかと思いきや、資金不足で存続に黄色信号だと伝えられています。
 悩み人
悩み人言論の自由はGAFAに決定権が握られているんだなぁ。



言論の自由は、通信インフラ技術、ネット上の言論空間維持、暗号技術の3つを持たなければ守れないんだよ。
詳しくは「メタバースがGAFA帝国の世界支配を破壊する!」をお読みください。
話を戻します。
日本でGAFAが生まれない理由は、以下です。
| ・ | 資金調達の環境がアメリカと比べて劣っていたこと |
| ・ | データセンターの費用の負担に耐えられないこと |
| ・ | 収益化まで至らないこと |
もちろん、この他にも、以下の理由があります。
| ・ | GAFA独自のビジネスモデル |
| ・ | 先行者利益 |
| ・ | グローバル展開や自国の人口が3億人以上いる規模感 |
| ・ | 優秀なプログラミング技術者が自国に多かった点(英語が母国語者は有利) |
中国もGAFAと似ているBATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)を、鎖国したことで作り上げています。
中国はそこまでグローバル展開しなくても、10億人以上の人口規模感があります。
そして、「メタバースがGAFA帝国の世界支配を破壊する!」の本に書かれていることを書きますね。
Google、Facebook、Microsoft(Skype)、AppleなどIT大手9社はスノーデンの暴露で話題になったPRISM計画というアメリカの全世界監視計画に同意していました。
で、IT大手9社はNSAに個人情報を提供しており、その見返りに資金の支援を受け、データセンターの費用に充てました。
さらに、電気代も補助があり、回線使用量も安くしてもらえたから、成り立っていたのです。
ちなみに、Amzonは参加していないようです。
ずっと赤字だったのですが、ビジネスモデルが評価されて、資金調達を続けられて、存続できたようですね。
スノーデンの告発後、PRISM計画は先細りとなりました。
金食い虫のデータセンターを賄うためにAmazonを除くGAFAは新しいスポンサーを求めました。
それが中国共産党です。
(ですが、Amazonと中国の関係は深いです)
GAFAと中国の深い関係については「メタバースがGAFA帝国の世界支配を破壊する!」をお読みください。
陰謀論は人間関係の相関図が重要です。
で、この本でも人物相関図が描かれており、陰謀論ほど酷くはないですし、著者の想像も若干、入っている印象を受けましたが、面白い本でした。
さて、YouTubeなどの動画配信サービスはとにかく金がかかります。
ユーザーが1つの動画を配信のためにアップロードすると、そのオリジナルを基に何十というファイルが作られます。
例えば、1分の動画をアップロードすると、30種類を超える動画が作られ、30分以上の動画をサーバー側は保存しないといけないのです。
そうなると、1時間の動画をアップロードする人が10万人を超えたら、「データ量だけで莫大なものになる」ことは容易に想像できるでしょう。
一方、ユーザー数がいないと、儲からないのがプラットフォームビジネスです。
そして、ユーザー数を獲得すればするほど、コストがどんどんかさんでくる矛盾を抱えています。
また、動画配信サービスの99%の動画の視聴回数(再生回数)は0回から数回程度で、広告もつかない無駄な部分です。
膨大な無駄(データ)を抱えながら、事業を存続させるには、以下の2つです。
早期に課金を成功させるか、徹底的にサーバーコストを抑えるか(Googleはこれをやってのけた)、です。
YouTubeは長年、赤字を垂れ流していました。
ですが、収益化を果たせたのは、Googleに買収されたのち、Googleの独自サーバーとGFSを利用してサーバー・コストが格段に下がったからなのです。
また、課金の方もハードルが高く、基本的にマーケットで1、2社しか勝てないのがインターネットの世界です。
オタク向け動画配信ではニコニコ動画などが典型例です。
広告依存にも限界があります。
だからこそ、上記で書いたように、個人情報のビッグデータをスノーデンに暴露されるまではGAFAは政府に買ってもらい、競争上の優位性を築いていました。
日本政府はベンチャー企業にこういう支援をしません。
また、GAFAのような先行者利益のある企業も、高品質な人材も少ない上に、米国・中国のような巨大な人口市場がありませんでした。
以上、日本にGAFAが生まれなかった、もしくは今後も生まれないであろうと僕が思う理由・説明でした。
さて、「結晶性知能を鍛えた証拠・証明としてのブログ」を僕は運営しています。
ビジネス・企画・社会情勢・時事ネタ系のブログです。
流動性知能IQ112の人間の考察がどの程度なのか、興味がある人は覗いてください。
IQがいかに創造力・文章力・ビジネス知識とは無関係か、分かるでしょう。



IQと創造力・文章力・ビジネス知識は関係ないってことだね。
今回、参考にさせてもらった本の著者である深田萌絵さんはかなり力作の本を量産しています。
読むと、知識が深まるでしょう。
以下の本を紹介しておきますので、興味がある人は読んでみてください。
「IT戦争の支配者たち 「半導体不足」で大崩壊する日本の産業」



この本は若干、小難しいけど、中国のスパイ活動がよく分かる内容だったよ。
深田萌絵さんの本は力作だらけだわ。
最後に、顔出し・声出し・撮影なしYouTubeを始めたのでお知らせしておきます。
(試しに1つ動画を載せておきます)
僕のYouTubeへは以下のリンクから飛べます。
https://www.youtube.com/channel/UCmikajHHXLoJm6zmevCYY1g
ではこの辺で。(3874文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。




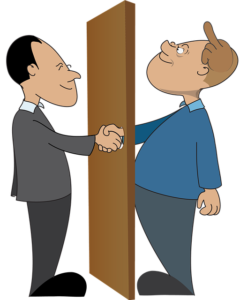



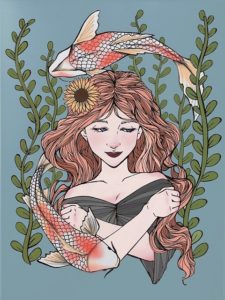

コメント