どうも、太陽です。(No27)
突然ですが、日本で賃金が上がらない理由を野口悠紀雄氏の「日本が先進国から脱落する日」という本を参考にしてまとめます。
興味がある人は続きをお読みください。
1 日本の賃金が上がらない理由。
いきなりですが、日本の賃金が上がらない分析を紹介します。
まず、2021年時点で、日本の賃金はアメリカの約6割程度になっています。
(最近は日本の賃金は韓国にも抜かれています)
これが起きた理由として、産業構造の転換に失敗した、つまりデジタル敗戦ということです。
そして次に、GAFAM(Google、Apple、Facebook(最近は社名をメタに変更)、Amazon、Microsoft)の5社の時価総額が、日本の上場企業の時価総額の合計の1.4倍になっていることを紹介します。
GAFAM5社の時価総額は、2021年10月末〜11月中旬時点で、1ドル=114円で計算すると、1072兆円になります。
一方、東京証券取引所の上場企業の時価総額は762兆円です。
GAFAMの雇用者は124万人(2019年)で、これらの人々だけで日本の上場企業の約1.4倍の価値をつくりだしたのです。
GAFAMの124万人の従業員のうち、Amazonが80万人なので引き、44万人になります。
ですが、これは2019年の情報データ・処理サービス部門の雇用者45.4万人とほぼ同数になります。
情報・データ処理サービス部門の2020年の1人あたり賃金は1ドル=114円で計算すると、2095万円になり、アメリカ全産業の平均賃金814.6万円の2.6倍です。
日本の平均賃金は371万円(金融業を除く全産業平均)なので、その5.6倍という凄まじい数字になります。
アメリカの「情報・データ処理サービス」に該当する産業は日本には存在しません。
そして、これはアメリカが昨今、作りだした新産業であり、「この新産業がアメリカを牽引している」と言えます。
ですが、この情報・データ処理サービスの雇用者45.4万人は、アメリカ全体の雇用者1億3217万人の0.3%しかなく、かなりの少数派です。
しかし、情報・データ処理サービス部門だけでない、同様の情報を中心とした経済活動を行なっている部門が他にあり、以下になります
| ・ | 出版(ソフトウェアを含む) |
| ・ | 証券・商品投資・保険。 |
| ・ | コンピュータデザインと関連サービス。 |
| ・ | 専門的・科学技術的サービス。 |
| ・ | 企業経営。 |
(P112から抜粋)
これらと情報・データ処理サービスを合わせて、「高度サービス産業」と言います。
これらの業種の雇用者は1539万人であり、全雇用者の11.6%を占めます。
さらに、「高度サービス産業」の範囲をもう少し拡大すると、以下になります。
| ・ | 「情報」(253万人) | (「出版」「情報・データ処理サービス」は、ここに含まれる) |
| ・ | 「金融・保険」(635万人) | (「証券・商品投資・保険は」は、ここに含まれる) |
| ・ | 「専門的・科学技術的サービス」(911万人) | (これは狭義の場合と同じ) |
| ・ | 「企業経営」(226万人) | (これも狭義の場合と同じ) |
(P113から抜粋)
以上4部門の雇用者を合計すると、2025万人となり、これは雇用者総数の15.3%であり、製造業の1184万人(9.0%)の2倍近くになります。
アメリカでは広義の「高度サービス産業」分野へ雇用者の移動が生じており、新産業を確立したのです。
日本では古い産業が存続しており、アメリカのように新産業に人が移らなかったことがいわゆる賃金が上がらないことの原因なのです。
2 賃金も成長率も高い産業は何か?
賃金が高く、成長率も高い産業や企業が多くなれば、国全体の賃金水準が上がります。
こうした企業や産業の賃金が高くなるには2つの場合があります。
第一は、高度な技術やビジネスモデルを持っているか、あるいは資本装備率(労働者1人あたりの資本ストック)が高い場合です。
(成長率も同時に高い企業や産業が多いです)
第二は、免許制や地域独占等の参入制限規制がある場合です。
(成長率は低い場合が多いです)
一方、成長率が高くなるにのも2つの場合があり、以下になります。
第一は、高度な技術やビジネスモデルによって成長する場合であり、賃金も高いので、「成長牽引型」になります。
第二は、需要が急速に増加している場合であり、ただし生産性の向上が望めない場合には賃金は低くなり、これは「貧乏成長型」と呼ばれます。
さらに、成長率が低く、賃金が低い産業もあり、これを「低成長低賃金型」と呼びます。
以上をまとめると、以下になります。
| 賃金。 | 成長率。 | ||
| ・ | 成長牽引型。 | 高い。 | 高い。 |
| ・ | 独占高賃金型。 | 高い。 | 低い。 |
| ・ | 貧乏成長型。 | 低い。 | 高い。 |
| ・ | 低成長低賃金型。 | 低い。 | 低い。 |
(P118から抜粋)
成長牽引型は賃金向上のためには不可欠な存在であり、「この産業をいかに確立するか?」が問われます。
アメリカには成長牽引型の「高度サービス産業」が確立しており、それがアメリカ経済を復活させました。
なお、アメリカの高賃金産業の中にも、独占高賃金型のものがあります。
例えば、石油・ガス採掘、鉄道、水道、公益事業、コンピュータ、電子製品、連邦政府職員、映画などです。
また、貧乏成長型産業もあります。
例えば、建設、運輸支援サービス、倉庫、社会支援、医療関係があります。
日本では、成長牽引型は情報通信業とガス・熱供給・水道業があります。
(電力自由化により、ガス・熱供給・水道業は本来なら独占高賃金型なのに、成長率が上がっています)
ただし、情報通信業の比率は小さく、全雇用者の3.9%しかいなく、これが日本の成長を阻害している要因と言えます。
日本における高賃金産業は、独占型が多く、例えば、電気業は典型例です。
しかも、日本では金融業も独占高賃金型になっており、アメリカでは金融業は成長牽引型なので、大きな違いです。
アメリカの金融業は高賃金な上に、成長しており、一つの理由としてフィンテックなど新しい金融サービスが産み出されている点があります。
組み込み型金融という新しい金融サービスでは、IT企業との共同で行うので、元々IT企業が強いアメリカにとっては相乗効果が見込めます。
対して、日本の金融業は高度成長期の預貸金利ざやビジネスから脱却てきておらず、特に地方銀行が典型例です。
(賃金水準が高いのは、参入規制のために過ぎません)
さらに、日本の場合に成長率が高いのは、貧乏成長型産業の、医療・福祉になってしまい、なぜなら高齢化社会だから、需要が高いからです。
(賃金は低いので、経済全体の賃金を押し下げます)
日本の賃金を上げるためには、成長牽引型が必要です。
そのための手段として規制緩和、基礎技術の開発のための大学改革による人材育成など、があります。
労働市場に介入して、政府が賃上げ要請をしても、賃金は上がりません。
(仮に、製造業の大企業が賃上げをしても、経済全体では微々たる影響です)
ところで、このリストには製造業が登場しませんが、中身を見ると、アメリカでは新しい製造業が誕生していることが分かります。
それは「ファブレス」(工場を持たない製造業)という形態の製造業であり、アップルが典型例ですし、半導体のクアルコムやエヌビディアも工場を持っていません。
これらの企業は製造工程を、台湾の鴻海やTSMCなどEMS(電子機器製造受託サービス)と呼ばれる企業に任せています。
そして、自らは開発、設計、販売など、付加価値の高い分野に集中し、つまり、製造業も情報産業になっています。
アップルは製造業ではなく、「情報・データ処理」に分類されている可能性が高いのです。
ちなみに、日本にはファブレス企業は、キーエンスなどごく少数しかありません。
なお、日本の賃金が低い理由として、新産業転換の失敗の他に、為替レートがあり、円安があります。
特に、2013年以降のアベノミクスから、異次元金融緩和政策で、積極的に円安政策が採られています。
ですが、本来なら新産業転換で生産性を上げて賃上げ化を図るべきだったのに、「円安によって他国に安く売る」という麻薬のような楽な方向性に向かってしまったのです。
「新産業転換などの生産性向上により、賃金が上がり、その後に物価が上がる」という順番なのです。
ですが、異次元金融緩和政策により、「物価が上がれば賃金が上がる」と政府は捉えてしまい、失敗したのです。
詳しくは「日本が先進国から脱落する日」をお読みください。
本には「日本の高度教育力はアメリカの7分の1」という見出しも書かれており、「日本の大学教育の悲惨さ」なども詳細に書かれています。
3 結局、日本の構造改革、成長戦略が機能しなかったということ。
さて、以下の記事を参考にしてまとめます。
https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g01236/
検証アベノミクス:経済政策として不十分だった真因
日本の失われた30年の停滞の理由として、いろいろな要因が挙げられています。
ですが、「賃上げ=経済成長」という視点で見ると、上記で述べた通り、新産業に転換できなかったことと、円安が原因になります。
アベノミクスとして、3本の矢(金融政策、財政政策、成長戦略)という経済学の教科書通りの政策が掲げられましたが、結局は金融政策の1本足打法に陥ってしまいました。
成長戦略によって、新産業に転換すべきだったのです。
ですが、政府にせよ、経済産業省にせよ、「ビジネスの素人も同然の人達」ですから、大企業の「円安にして助けてくれ」という要望をそのまま聞いてしまいました。
そして、ビジネスモデルの変革や技術革新やデジタル化を進めませんでした。
記事を書いた著者の加谷珪一氏は「社会保障の不安を軽減させなかったことも日本停滞の原因である」と書いています。
僕もその意見にある程度、頷いていました。
高齢化により、イノベーション的製品がアメリカと比べ売れにくいことや、生産年齢人口の減少で人材不足な点や、権力者の高齢者とそれを支持する高齢者の思想により、デジタル化が進まなかった点などを、僕は「日本停滞の原因だ」と捉えていました。
デジタル庁も「今更か」と思いますし、共通テストに情報という科目を加えるのも「今更か」と「全てが何周遅れなんだ!」と思う政策ばかりです。
Windows95が発売された1995年からデジタル敗戦は始まっており、現在は2022年ですから、27年も経っており、手遅れ感が半端ないのです。
まぁアメリカのような新産業転換の劇的な成功例は稀ですから、完全には真似できません。
ですが、日本ももう少し、「成長牽引型の産業の割合を増やすべきだ」と思います。
(アメリカの15.3%に対し、日本は3.9%なので少なすぎます)
ICTのことを熟知している人を政治家にし、政策を進めるべきでしょう。
「ICT大国」を今更、掲げるのも遅すぎる感がありますが、全力で追いつく姿勢がないと、これからもデジタル敗戦が続くでしょうね。
中小企業はAmazonのKindle貯金、YouTube貯金、Googleの検索エンジン貯金(ブログやHPなど)で宣伝をしないと、生き残りづらくなっています。
Kindle貯金とは「良質な電子書籍を出せば良い宣伝となること」を意味します。
YouTube貯金とは「良い動画をアップすれば強力な宣伝となること」です。
Googleの検索エンジン貯金とは「表示画面で上位3位ぐらいまでに入れば強力な集客ツールとなること」です。
で、Amazon、Googleの2社は売上のうち、手数料で抜いていくのです。
(完全に、日本はICT植民地です)
他にはX(旧Twitter)やInstagramや、Tictokも宣伝媒体としての選択肢にありますが、効果は様々です。
大企業は知名度と従来のTVCMなどで戦っていけます。
ですが、ベンチャーや中小企業は集客するためには、Kindle貯金、YouTube貯金、Googleの検索エンジン貯金をするのが王道なのです。
このような事態になるまで放置?しておいたのが日本の失政であり、デジタル敗戦ということになります。
4 安倍政権のアベノミクスから方向性がずれていた!?
そして、致命的なのが安倍政権のアベノミクスです。
ブレーンを高橋洋一氏にしていましたが、彼は経済学には詳しかったのですが、経営学(成長戦略)には無知でした。
高橋洋一氏野著書を読むと、以下のことが書かれています。
| ・ | 雇用の確保(失業率の低下と就業者数の増加)ができれば60点の及第点、所得の向上があれば尚よし、という視点。 |
安倍政権は1953年以降の29の歴代政権において、「失業率低下で1位、就業者数増加で2位という断トツの結果を残している」と自画自賛しています。
つまり、最初から目標設定が低いわけです。
現在、「日本人の給料が上がらない、低い」と騒がれていますが、ブレーンの高橋洋一氏は「給料は上がればラッキー」ぐらいにしか捉えていなかったのです。
雇用の確保であれば、極端な話、「公務員的な仕事を無理やり増やせば達成できる」と思います。
(そこに、人手不足が加わったのですから、余計に失業率は低下しやすい環境でした)
成長戦略を描くのであれば、今回の記事で挙げた新産業への移行が重要でしょうが、それも描きませんでした。
もしくは競争力をつけるのであれば解雇規制の撤廃をすれば良いのでしょうが、それも既得権益の抵抗を恐れてやりませんでした。
解雇しやすくすれば、流動性が高まります。
そして、人が成長産業に移ったり、非効率な企業は淘汰され、皆、生き残るのに必死になり、スキルを磨きます。
ですが、安倍政権は手をつけないで、安易に金融緩和をして、円安誘導に走ったのです。
もちろん解雇しやすくなったら、社会不安は増し、失業率も上がります。
ですが、それは必要な痛みだったかもしれなかったのです。
(解雇せずとも、猛烈な再教育・学び直しは加速すべきでした)
現在、岸田政権はリスキリングを提唱しています。
ですが、ブレーンの高橋洋一氏は雇用の確保が第一ですから、当然、解雇規制の撤廃に手を出しませんでした。
また、「給料を上げるために新産業に移行するべき」というプランも描きませんでした。
企業で成果を出す場合、設定すべき変数やKPIが重要です。
ですが、安倍政権のブレーンの高橋洋一氏の変数は「雇用の確保」が第一であり、「所得の向上」は真剣に考えていなかったのですから、「そりゃ結果が出ませんよね?」って話です。
しかも、長年の金融緩和による悪影響である円安が今頃、出始めています。
目標設定や変数やKPIを間違えると、「当然、目標は達成しない」というオチでした。
以上、日本の賃金が上がらない理由を述べてきました。
参考になる方がいれば幸いです。
ではこの辺で。(6081文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。





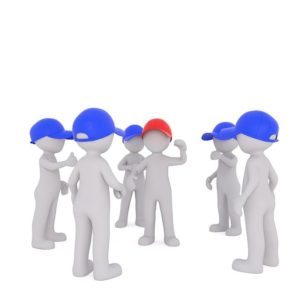




コメント