どうも、太陽です。(No16)
突然ですが、ブルーオーシャン企業の実例として5社、具体例をあげます。
そして、ブルーオーシャン企業が「いかに値上げがしやすいか」を説明します。
気になる方は続きをお読みください。
1 ブルーオーシャンとレッドオーシャンの説明。
まず、ブルーオーシャン戦略について説明します。
ブルーオーシャン戦略とは、「競合がいない、もしくは少ない市場「ブルーオーシャン」(青の海)で戦う戦略」のことです。
ブルーオーシャンは需要が見えづらく、新規開拓することなので挑戦者です。
また、需要があるとわかっても、一人勝ちはずっとは続かず、新たな参入者が増えてくるのが弱点です。
逆に、レッドオーシャンとは「(赤い海・血の海)」という通り、競争の激しい市場で、価格やクオリティで激しい消耗合戦が繰り広げられます。
レッドオーシャンは競争が激しいくらいですから、明確で手堅いニーズが既にあり、そこで勝てれば大儲けできるかもしれません。
2 ブルーオーシャン企業の価格値上げは許される。事例1
さて、ブルーオーシャン戦略を今でも使っている企業を僕は5社見つけました。
一つ目はQBハウスです。
1080円だった値段(2014年2月に1000円から値上げ)を2019年2月から1200円にするというニュースが流れました。
以下の記事です。
「QBハウスの「価格破壊」と「料金値上げ」というタイトルです。
https://blogos.com/article/318047/
QBハウスは完全にブルーオーシャン企業であり、競合がほぼいません。
一般の理容店は3000円台であり、1時間くらいかかるのがざらです。
それに対して、QBハウスは待ち時間がほぼなく、10分で終わります。
(その分、美容師との会話もないので、会話が苦手な人には良いでしょう)
QBハウスは競合がいないので、まだまだ値上げしても客が減りそうもありません。
そういう意味で、ブルーオーシャン市場はかなり魅力的です。
3 ブルーオーシャン企業の価格値上げは許される。事例2
2番めのブルーオーシャン企業はガリガリ君を発売している赤城乳業です。
ガリガリ君も、2016年に従来の60円(税抜き)から、70円(税抜き)に値上げしました。
ガリガリ君は、氷系アイスでは競合があまりありません。
敢えて挙げると、BIGスイカバーです。
価格は105円のようです。
ガリガリ君より大きいサイズなので、値段も高めになっているのでしょうね。
僕はダイエット意識もあり、氷系アイスを好んで買います。
で、買うとしたら「ガリガリ君 (ソーダー味は嫌い)か、BIGスイカバーの2択」になっています。
コンビニで買うからでしょう。
(セブンイレブンです。ローソンにはガリガリくんのソーダ味しかないのが残念な点です)
ガリガリ君もあと10円値上げして、80円になったとしても、なんとか持ちそうな気がします。
BIGスイカバーという競合がQBハウスとは違い、いるので、そこまでの値上げができません。
ですが、やはり値上げしてもある程度許され、価格競争が激しくありません。
ブルーオーシャン企業と言えるでしょう。
4 ブルーオーシャン企業の価格値上げは許される。事例3
3つ目はニンテンドーの携帯ゲーム機、Switchです。
有機ELモデルは、強気の価格設定の約3万2000円〜3万8000円レベルです。
(Switch Liteは約2万円です)
ここまで強気の価格設定ができるのはブルーオーシャンだからでしょう。
と一瞬、思われたかもしれませんが、実はスマホが競合です。
スマホゲームにより、携帯ゲーム機の売れ行きが鈍っている可能性があります。
とはいえ、携帯ゲーム機は子供用としては「まだまだ手堅いニーズがある」と僕は思っています。
大人はスマホに移行してそうですが、子供(小学生)にスマホをもたせるのはまだ早く、手軽な携帯ゲーム機がないのです。
だから、子供用ゲーム機として、Switchはここまで強気の価格設定ができるのでしょう。
Switch Liteであれば約2万円なので、子供に持たせるにはちょうどいい価格設定です。
ソフトも高いのが多いですが、親御さんが買うので問題ないのです。
ニンテンドーは無借金経営で有名ですが、過去にバーチャルボーイやWii Uや3DSで失敗した経緯があります。
よって、「ゲーム産業とはギャンブルである」と強く認識しています。
とはいえ、ニンテンドーにはニンテンドーしか作れないキラーソフトもたくさんあり、そこが強みですね。
ニンテンドーは過去のソフトの遺産が多いので、そう簡単に牙城は崩せないでしょう。
2019年にGoogleがStadiaでゲーム産業に参入するとなった際は、「黒船だ!」と騒がれ、「ソニーやニンテンドーが食われる!」と大騒ぎになりました。
ですが、蓋を開けてみればビクともしませんでした。
ゲーム産業はしばらくの間は、ソニー、Microsoft、ニンテンドーの牙城争いになりますかね。
5 ブルーオーシャン企業の価格値上げは許される。事例4
4つ目はNetflixです。
Netflixは莫大な予算をかけて、独自のコンテンツを作っています。
競合のAmazonPrimeビデオより、優位でしょう。
(Amazonは片手間で、本業じゃない点もあります)
以下の記事によると、カナダやアメリカで、またNetflixが値上げしたようで、日本にも波及しそうです。
Netflixの月額会員料金が最大2ドル値上げへ
Netflixは少しずつ値上げしても、ライバルがほぼいなく、価格勝負の世界じゃないので、まさにブルーオーシャンでしょう。
Netflixでしか見られない独自コンテンツという戦略により、「Netflixから離れられないユーザーはかなりいる」と推測できます。
僕は映画は年に3本観ればいいほうなので、Netflixの会員にもなっていないですが、映画・ドラママニアにとっては離れられないサービスなのでしょうね。
と思っていましたが、昨今、Netflixの会員数が頭打ちになっており、広告付きの安価なプランを始めています。
最強の企業と思われたNetflixも「会員数の頭打ち」という現実に直面しています。
6 ブルーオーシャン企業の価格値上げは許される。事例5
5つ目は日経新聞になります。
日経新聞はビジネスマンに根強い人気があります。
ビジネス(株情報含む)に特化した新聞は他にはあまりありません。
NewsPicksはビジネスマン向けですが、まだまだでしょう。
東洋経済オンラインやダイヤモンドオンラインも競合に近いですが、コンテンツの質と量が日経新聞に負けています。
KindleUnlimited(電子書籍)やDマガジン(雑誌)なども競合になりません。
読売新聞や朝日新聞や毎日新聞とは種類が異なっていますし、年々、購読者が減っています。
・朝日新聞の発行部数は約500万部であり、価格は朝夕刊セット版で4400円です。
・読売新聞の発行部数は約750万分であり、価格は4400円です。
・毎日新聞の発行部数は約200万部であり、価格は4300円です。
・日経新聞の発行部数は約200万部であり、価格は強気の4900円です。
(電子版の有料会員数が約82万人であり、電子版単体の価格は驚きの月額4277円です)
新聞購読者の大半は中年以上であり、読売や朝日や毎日が仮に電子版に移行すると、解約されそうです。
電子新聞なんてほぼ成り立たないビジネスモデルなのですが、日経新聞だけはマニアユーザーの心を掴んで、成功しているのです。
そういう意味で、日経新聞(電子版)は高価格を維持でき、「ライバルがほぼいないブルーオーシャンと言える」でしょう。
思えば、日経新聞と関連があるテレビ東京も、ビジネスマン向けやアニメなどのマニアックな放送をしており、変わった放送局なのです。
しかし、その差別化意識が功を奏しており、YouTubeでのテレビ東京公式チャンネルの会員数は約122万人です。
日テレ公式チャンネルの登録者数は約66万人ですし、TV朝日のチャンネルも約44万人ですし、TBSの公式チャンネルも約64万人いますが、テレ東が勝っています。
ちなにに、YouTubeチャンネルでの日経テレ東大学(ひろゆきやイェール大学の成田氏が有名)はチャンネル登録者数が約100万人を超えていましたが、内紛があり、番組中止に至りました。
ではこの辺で。(3715文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。




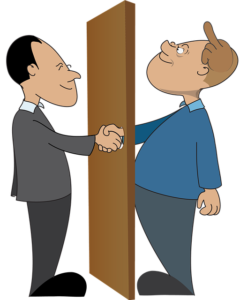



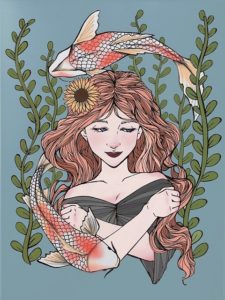

コメント