どうも、太陽です。(No47)
 悩み人
悩み人2022年7月29日現在で、132円台だね。
2022年10月27日時点では145円台まで円安になったよ。
iPhoneが高すぎて買えない日が来るのかなぁ。
iPhoneは2022年7月に値上げされた。
また、以下の記事によると、VRヘッドセット「Meta Quest」は128GBモデルが3万7180円から5万9400円になった。
さらに、中国製のXiaomiもタブレット端末、ワイヤレスイヤフォン、スマートウォッチなど6製品を値上げし、パナソニックは、家電製品を現行価格から3~23%程度値上げするという。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2207/29/news139.html
値上げはiPhoneだけじゃない 8月から価格が変わるハードウェアまとめ



円安になると、輸入品が高くなるけど、それは食料品やエネルギー(石油など)だけでなく、海外からの電機製品も高くなるね。
はい。
仮に200円台の超円安時代が到来したら、iPhoneは高すぎて買えなくなり、食料品も、エネルギーに関係する電気代なども爆上がりするかもしれません。
ちなみに、150円の超円安時代ですが、以下の記事によると、九電は過去最高益です。
https://mainichi.jp/articles/20231102/k00/00m/020/070000c
九電が過去最高益 1498億円、燃料価格下落で 9月中間決算
理由は天然ガスなどの燃料価格が下落した上に、原子力発電所の稼働が増えて燃料費が減った点にあります。
ここで、日本国が「将来、円安か円高どっちがいいのか?」を本気で考え、「それに順応・適応できる国家作りを目指すことが求められる」といえます。
この記事では、「超円安時代に適応するならどういう国家づくりがいいのか」を考察していくので興味がある人は続きを読んでください。
(「なぜ、円高時代を想定しないか?」は記事を読めば分かります)
(異論は認めます)
1 日本は輸出+消費のハイブリッド国家。
以下は、主に1980年代までに通用した理屈です。
(突然の話題ですが、ついてきてください)
「日本は輸出主導型国家だ」と言われていますが、輸出主導型といっても以下の2つに大きく分けられます。
| 1 | 純粋な輸出主導型経済。 |
| 2 | 国内消費市場とのハイブリッド型。 |
1の純粋な輸出主導型経済は、GDPに占める輸出の比率がかなり高く、国内の消費の影響はあまり大きくありません。
とにかく輸出しまくり、輸出企業が支払う賃金や設備投資が国民所得の大半を占めます。



典型例として、輸出依存度が高いドイツ(45%)、オランダ、北欧諸国などがあるね。
2の国内消費市場とのハイブリッド型は、GDPに占める輸出の比率はそこまで高くなく、日本が代表例ですが(輸出依存度10〜15%)、国内の製造業は輸出も行います。
(国内へも積極的に販売します)



輸出企業が支払う賃金や設備投資に加え、国内の消費市場もGDPに貢献するね。
はい。
ですが、ハイブリッド型である日本は、国内消費市場の影響も大きいのですが、経済成長のエンジンとなっているのは製造業の輸出であり、国内労働者の賃金も製造業のほうが圧倒的に高いです。
「日本経済は内需中心」と言われたこともありましたが、やはり輸出主導型なのです。
輸出主導型の国の場合、外需に頼っているので、外国に決定権があります。
「海外に需要があるかどうか、景気が良いかどうか」にかなり左右されます。
輸出主導型の景気拡大路線は以下になります。
| 1 | 企業は海外需要に対応するために、工場など生産設備を増強し、国内の設備投資が拡大。 |
| 2 | 企業が設備投資を強化するということは、資材などをたくさん購入することなので、多くの企業収益が拡大。 |
| 3 | 拡大した企業収益は最終的には賃金になり、国内労働者の所得を増やす。 |
| 4 | 労働者は賃金が増えると余裕ができるので、消費を増やす。 |
| 5 | 消費が増えると、今度は国内の店舗などに対する設備投資が増え、それがさらに所得を増やし、消費を拡大させる。 |
純粋な輸出主導型経済は、設備投資の寄与度は大きいのですが、ハイブリッド型(日本)の場合には、設備投資の拡大が消費の拡大を促し、さらに国内消費者の購買力の増加も成長に拍車をかける構図になります。
ここまでは1980年代までに通用した理屈でした。
以下は、1990年代に起きたパラダイムシフトの話です。



1990年代、特にWindows95が発売されたぐらいからはPC、ITの時代が到来したね。
はい。
で、ITの時代において、日本は大敗北を喫しました。
例えばITの投資の金額(ハードウェアとソフトウェアの総額)は、日本だけが25年以上にわたって横ばいで推移しました。
その間、米国は3.3倍、フランスは3.6倍、IT化に消極的だったドイツでも1.6倍に拡大させています。
ドローンやEV(電気自動車)は米中の独壇場です。
例えば中国製のドローンは安価で汎用品な部品でもソフトウェアを駆使して安くて質の良い製品を作り出しています。
EVでも、ソフトウェアが設計基盤にあるテスラなどにボロ負けしており、中国のEVはすべてテスラなどを参考にしていて、日本のEVはかなり出遅れています。
クラウドの分野(データセンター(AWSなど多数))でも、ハードウェアに重点を置きすぎた日本企業は、ハードウェアが壊れることを前提にソフトウェアを駆使して設計されたGoogleやAmazonやMicrosoftなどにボロ負けしています。



ソフトウェアを駆使したITや製造業の戦いで、日本は米中にボロ負けしているんだね。
2 インフレと円安時代が確定した日本。
ここからは「インフレと円安が確定した日本」というテーマで書いていきます。
まず、日本は金利を大幅に上げたくても上げられない前提があります。
以下の記事でも書いています。


日本語という言語「日本が韓国化する日」
なぜなら、例えば金利を仮に5%まで上げたら、利払い費だけで日本の国家財政が危機的になります。
さらに、住宅ローンも連動して上がり、社会が混乱します。
金利を大幅に上がられないとしたら、待っているのはインフレです。
インフレになれば、カネの価値が下がり、借金をしている人の負担は減り、大幅な借金大国の日本にもメリットがあります。
ですが、株式投資じゃなく預貯金だけの人は物価がかなり上がるので、どんどん現金が減って、貧乏になっていきます。



インフレ(=物価の上昇)とともに、賃金が上がったり、株式投資で増やすことができれば、そこまで困らない。
だけど、大抵の場合、資産を持っているのは高齢者であり、若者は投資する元手があまりないよね。
はい。
となれば、賃金を上げることが大事であり、インフレ手当を出す企業も増えてきたけど、持続できるかどうか、です。



岸田首相の新しい資本主義は「インフレ時代に備えて株式投資せよ!」というメッセージだったのかもしれないけど、若者には元手がそこまでないよ。
はい。
仮に株式投資できる元手があっても「将来性がない日本に投資するより、米国株式だ!」となり、日本の株価はそこまで上がらないかもしれません。
(結局、GPIFが買い支える構造は変わりません)
さて、インフレ(=物価の上昇)ということは、カネの価値が下がることであり、日本円の価値も下がるので円安になります。
というわけで、インフレと円安時代が確定したのが日本の将来なのです。
(異論は大いに認めます)
ここからは「インフレと円安時代に適応した日本の姿とはどんなものか?」を考察していきます。
3 インフレと円安時代に適応した日本の姿。
まず、円安は最悪200円まで想定しておきます。



円安になると、輸入品の値段が上がるので、食料品、エネルギー、海外の電機製品などは値上がりするね。
はい。
となれば、食糧自給率をもう少し上げること、原発の増設、「iPhoneが高すぎて買えなくてAndroidや中華スマホなどになるので日本製のチャンスかも?」ということになります
半導体工場を熊本に作りましたが、工場の国内回帰は進むかもしれません。
輸入をなるべくしないで済ます、つまり自給国家にならないといけなくなります。



EV(電気自動車)は海外向けに絞り、国内はガソリンを使わない燃料電池車(FC車)や水素自動車なんて路線はどうだろう?
ガソリン自動車を使い続けると、ガソリンの値上げにいずれ適応できなくなります。
かといって電気自動車は原発をかなり作らないといけなくなり、無理筋です。
(まぁ燃料電池車でも原発増設は必要ですが)



原発再稼働はドイツでも実行されたそうだけど、現実の前には、つまり電力不足の前には、原発再稼働はもちろん、新規の原発増設すら考えなくてはいけないってことか。
さて、日本の1次エネルギー供給(2020年)のデータだと、石油(38%)、天然ガス(22%)、石炭(27%)、原子力(2%)、水力(4%)、再生可能エネルギー(7%)です。
また、原子力発電の燃料であるウランは輸入依存ですが、一度輸入すると、長期間使用でき、使い終えた燃料の97%は資源として再利用できます。
安全性を考えると、従来の巨大システムの原発ではなく、小型原子炉であれば常温冷却可能で格段に安全です。
小型原子炉であれば地産地消が可能になり、地域分散型になります。
しかし、以下の記事によると、核融合発電の実現可能性はけっこう高いようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4bea9be9983a4498c61644e9347e71f3a895544
見えてきた核融合発電の実用化、中国が頭一つ抜け出す勢い
「核融合発電に量子コンピュータと同程度かそれ以上に投資すべきだ」と僕は考えます。
「インフレ・円安時代に適応せざるを得ないのが日本の将来図なのか?」と思われた人もいるかもしれません。
ですが、野口由紀夫氏の「円安が日本を滅ぼす」という本も発売されていますし(まだ未読)、以下の本にあるように「円安は悪であり、日本の将来はアメリカや将来の中国のような消費主導型になるべきだ!」という理屈もあります。
加えて、以下の記事で、加谷珪一氏は「円安は150円台が目安であり、住宅は持ち家がいい」と主張しています。参考までに。
https://news.yahoo.co.jp/articles/68ac4506a0800f683dd5df64a98ea470f78868fc
超円安の時代:目安が1ドル150円となる理由、住宅は持ち家がいい理由
日本の将来像については以下の記事で続きを書いているので、ぜひ読んでください。


「日本の労働生産性は本当に低いのか?」という点について論じつつ、実はそうではなく、さらに日本の未来の国家像について考察しています。
議論の余地が大いにあるテーマです。
皆さんも考えてみてはどうでしょうか?
では、この辺で。(4085文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。





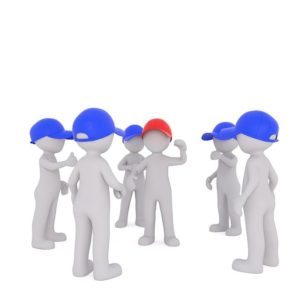




コメント