どうも、太陽です。(No67)
突然ですが、「里親は儲かるのか?」とふと里親について考えたことがある人なら、思い浮かべたかもしれません。
ですが、それは「里親の内情を知らない人の考えだ」と思います。
「里親になりませんか 子どもを救う制度と周辺知識」という本を読んで詳しく調べてまとめましたので、このテーマに興味がある人は続きをお読みください。
1 里親についての詳しい説明。
里親についての詳しい説明をします。
まず、里親には以下の種類があります。
| ・ | 養育里親。 | |
| ・ | 専門里親。 | 児童虐待等を受けた子供や、非行等の問題がある子供を養育する里親。 |
| ・ | 養子縁組里親。 | 養子縁組が可能な要保護児童を養育する養子縁組を前提とした里親。 |
| ・ | 親族里親。 |
そして、里親は合計約1万2315人が登録や認定をされています。
養育里親は約1万136人です。
そのうち3441人の養育里親に、4235人の子供が委託されています。
専門里親は702人です。
養子縁組里親の登録数は4238人です。
そのうち317人の縁組里親家庭で、321人の子供達が縁組成立を目指して養育されています。
親族里親の認定数は588人です。
すべての里親を合計すると、4379人の里親家庭に、5556人の子供が生活していることになります。
里親の活用率としては、約35%程度です。
つまり、里親を存分に活かすには約3倍の里親数が必要になる計算です。
加えて、ファミリーホームというモノが全国に372ホームあり、1548人の子供が委託されています。
つまり、合計7104人の子供が、一般の家庭である里親家庭・ファミリーホームで生活しています。
7104人という数字は、児童養護施設と乳児院の入所児童と、里親とファミリーホームの委託児童の合計3万4690人に対して、約20.5%にあたります。
つまり、いまだに8割の子供達が児童養護施設や乳児院で生活しており、里親に引き取られた子供達は幸運なのです。
ちなみに、児童養護施設には2万4908人、乳児院には2678人の子供が入所しています。
里親になる要件は細かく決まっていて、さらに研修制度(5年ごとに更新)もあります。
詳しくは以下の本に譲ります。
(名著です)
ところで、児童養護施設への措置入所や里親等に措置委託された子供が4万375人います。
その中で、里親とファミリーホームに委託された子供は6895人です。
預けられた理由は以下です。
| 1位 | 虐待。 | 全体の40%(2770人) |
| 2位 | 父母の精神疾患。 | 全体の約13%(919人) |
| 3位 | 父母の死亡。 | 全体の約11%(768人) |
| その他。 |
児童養護施設の場合は以下です。
(2万7036人います)
| 1位 | 虐待。 | 45%(1万2210人)。 |
| 2位 | 父母の精神疾患。 | 16%(4209人)。 |
| 3位 | 経済的理由。 | 5%(1318人)。 |
| 4位 | 拘禁。 | 5%(1277人)。 |
| その他。 |
上記の理由から切り離されたわけで、多くの保護された子供たちは、問題を抱えています。
学業状況に関していうと、里親で23%、ファミリーホームで38%の子供に遅れがあるとのことです。
しかし、里親家庭の63%の子供は特に問題がありません。
通学状況でも、77%の子供が普通に通っています。
一方で、里親家庭に委託された子供達の心身の状況は25%にあたる1340人が何らかの障害を抱えており、以下のようになっています。
| 1位 | 知的障害。 |
| 2位 | 広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)。 |
| 3位 | 注意欠陥多動性障害(ADHD)。 |
| 4位 | 反応性愛着障害。 |
ファミリーホームだと、47%にあたる703人が同じ傾向にあります。
つまり、問題児が普通の家庭の比率より多いといえます。
さて、以下の記事には、メンタルヘルスに重要なのはマタリング(他の人から重要視されること)だと書かれています。
記事から一部を抜粋します。
認知度:あなたに注意を払ってくれる人がいるかどうか?
重要度:あなたの幸福に心から関心を持ってくれる人が周囲にいるかどうか?
信頼度:サポートやアドバイスを求めて、あなたのところにやってくる人がいるかどうか?
これが満たされていないと、メンタルヘルスや人生の満足度に悪影響があります。
記事にはマタリングテストが掲載されており、僕がやった結果は以下です。
認知度は3.5、重要度は3.2、信頼度は4.0でした。
(3.5あれば高い方だそう)
あなたに注意を払ってくれる人がいるかどうか?の認知度は、児童養護施設や乳児院の入所児童は感じにくいでしょう。
ですから、里親の役割はかなり大きいのです。
(信頼できる大人がいるのは大事)
ところで、里親は養子縁組とは違い、実親がいて、いずれ元の場所に戻すのが前提の仮の親です。
しかし、実の家族と交流がある子供は里親家庭では28%(1511人)しかいません。
70%(3782人)はまったく交流がありません。
ファミリーホームの場合は、交流のある子供が54%(821人)で、まったく交流のない子供は37%(559人)です。
児童養護施設の場合は、2万7026人いますが、交流のある子供は72%(1万9336人)、交流のない子供が20%(5391人)です。
つまり、里親の子供達は里親以外に拠り所がない子供が多いです。
また、養子縁組に将来的に結びつける里親も少数ながらいます。
そして、里親家庭の子供5382人のうち、実親家庭や親族に引き取られる見通しのある子供は11%(583人)しかいないのです。
養子縁組の予定が12%(654人)です。
自立まで里親家庭で過ごす子供は69%(3696人)います。
里親はいくら国から金をもらえるとはいえ、壮大なボランティアか、愛のある人なのです。
(実の子じゃなく、他人の子を一時的に育てるのですから)
あと、里親の76%(3208家庭)が、委託児童は1人です。
2人委託されている里親は19%(789家庭)で、3人委託されている里親は4%(166家庭)、4人委託されているのだと1%(42家庭)です。
里親は、委託される子供の数は4人まで(自分の子供を含めて6人まで)という規定があります。
ちなみに、どの子供が来るかは児童相談所の判断です。
また、里親委託には実親の承認も必要です。
ただし、年齢や性別などは、里親の希望も踏まえて検討されます。
2 里親は儲かるのか?
ここで、本題の「里親は儲かるのか?」のテーマに移ります。
里親になると、里親手当(子供1人あたり毎月9万円)と里親受託支度金(子供を新たに受け入れた際に4万4630円)と一般生活費(月額5万1610円。乳児の場合は5万9510円)などがもらえます。
専門里親の場合は、問題児を扱うためか、里親手当だけで、子供1人あたり毎月14万1000円もらえます。
なお、養子縁組里親と親族里親は里親手当はありません。
ほかにも、たくさんの種類のモノが支給されます。
詳しくは本を読んでください。
つまり、里親は確かに愛があり、適性のある人しかなれませんが、金銭面でのリターンもそれなりにあります。
しかし、普通の子供と比べて、問題児が多く、負担が多いので、壮大なボランティアか愛のある人しか務まらないと思われます。
(5年ごとに更新の研修もありますし)
子供1人あたり毎月9万円もらえるかといって、「他人の子供を育てますか?」という論点になりますね。
(一般生活費の月額5万1610円は生活で消えてしまうでしょう)
ちなみに、社会的養育が必要な子どもの生活の場は、児童養護施設や乳児院に入所している子どもが79.5%を占め、里親等は20.5%に過ぎません。
これを逆転させたいのですから、国の本気度は高いです。
3 少子化問題解決策として、養子縁組や里親制度も加えたら、どうか?
いきなりですが、以下の僕の記事からの引用です。

岸田首相の「異次元の少子化対策」を超える「究極の少子化問題対策案」
ここからは僕の考えた究極の少子化問題対策案を書きます。
それは婚姻数の増加を狙うよりも、既婚女性に焦点を当てる案です。
既婚女性は平均約2人を産んでいますが、さらに3人目を産んでもらいたいのです。
で、現在の世帯課税から個人課税(N分N乗方式)へ移行させるのです。
フランスで効果実証済みの政策のようですが、若干、アレンジを加えます。
3人目の子供を産んだ世帯には、所得税を大幅に減税します。
「3人目は年齢的にも無理」という世帯には、代替案として里親制度を活用します。
里子でも3人目として受け入れた場合、所得税大幅減税を適用します。
で、「3人目の子供を持った家庭には所得税大幅減税にし、里親も代替可能にする」と、以下の流れを僕は期待しました。
1 里親の金銭面での厚遇と所得税大幅減税のインセンティブにより、里親登録者が増える。
↓
2 里親登録者が増えれば、毎年、妊娠したあとの人工中絶の約15万件を産ませられるのでは?という見込み。
ある調査によると、心臓移植を希望する人の数は2020年3月31日現在で1万4505人です。
一方で、実際に臓器移植が行われたケースは年間480件(2019年)です。
里親登録者と妊娠した人口中絶の約15万件の比率が「これくらい毎年あればいいなぁ」と感じます。
(供給が余りまくっており、需要を十分カバーできる)
しかし、以下の記事にあるように、反感も買っています。
「すべてが経済的な理由からの人口中絶なら納得できるがそうじゃない」はそのとおりですね。
↓
3 しかし、現在の里親登録者数はいくら周知・告知活動がほとんどなされていないとしても、約1万2315人しかいません。
しかも、「他人の子供や問題児?をいくら金がもらえるからといって育てるか」かなり疑問符に。
(里親は適性がかなり必要でもある)
↓
4 しかし、とりあえず、この案を説明して、「里親がどれだけ集まるか?のサンプル調査はして欲しいなぁ」と思う。
フランス式の所得税減税策でも効果はあるかもしれませんが、僕は里親制度を追加しました。
また、里親手当の毎月9万円と、一般生活費(月額5万)をざっくり計算して、仮に10年養育したとすると、1680万円になります。
(他の費用も含めてざっくり2000万としましょう)
ひろゆきの提案した「1人産めば1000万円」より、多い額です。
しかし、僕の案の良い点は毎年の人工中絶の15万の増加分だけに2000万がかかるという点です。
ひろゆきの案だと、毎年の80万人の出生数に加えて、仮に20万人増加したら、100万人に1000万円を配らないといけないのです。
(つまり、毎年10兆円かかります)
ですが、僕の案だと増加分だけになるので、ひろゆきの案より2倍多くかかったとしても、コスパが良いのです。
さて、里親ではなく、養子縁組にする方が子どもに愛着が湧くでしょう。
養子縁組は里親手当は出ないのですが、個人課税(N分N乗方式)にし、2人目、3人目をもったら、所得税減税にすれば「養子を持とう」というインセンティブが働くかもしれません。
その際、妊娠したあとの人工中絶の約15万件の10万件ぐらいが産まれるだけでも、相当な少子化対策の効果としては大きいです。
アメリカのある州のように、人口中絶を完全に禁止するのは難しいでしょう。
レイプや予期しない妊娠などがあるからです。
さらに、人口中絶の場合、多胎児の子ども、先天的疾患や発達の遅れのある子どもが普通に比べたら、「生まれやすい」と思われます。
しかし、経済的に産めないという理由なら、養子縁組のマッチングの場を作り、マッチさせれば、少子改善につながるかもしれません。
養子縁組のマッチングでは、出会いのマッチングだけでなく、養子を育てることの情報共有の場としても機能して欲しいと願います。
今は児童相談所が担っています。(また、全国に養子縁組あっせん業者があります)
また、「所得税減税効果をどれだけアピールするか?」または「その効果を国民がどれだけ認知するか?」ですね。
子どもを持った方が経済的に得という社会になれば、動機づけは生まれます。
ひろゆきも僕の案に乗っかったのかは不明ですが、似たような案をツイートしています。

ちなみに誤解されないように繰り返しますが、養子縁組については里親手当は出ません。
(金がもらえません)
しかし、個人課税(N分N乗方式)で、2人目、3人目に里親も追加されれば、里親は所得税減税も受けられる上に、里親手当ももらえて、相当に経済的には有利になります。
また、養子縁組については、金をばらまく必要はないので、コスト削減になります。
里親と養子希望組(妊娠した人口中絶の約15万件のうち、10万件ぐらいとマッチングすれば良し?)のマッチングを国が推進します。
また、結婚していて子どもを産む平均人数は約1.9人ですが、少子化が進んでいるのは未婚率が上がっているからなのです。
30・40代の男女の親との同居率が6割を超えており、仮に結婚したら、実家をでなくてはならず、「家を新しく借りる」となると、生活レベルが確実に下がります。
ですから、結婚する世帯への住宅支援も大事になります。
(イギリスやフランスは国民の約2割が住宅支援を受けているが、日本にはない)
ちなみに、僕の少子化案にも弱点があります。
それは以下の記事にあるように、住宅も高騰していますし、そもそも家が狭く、「3人の子どもが快適に住めるのか?」問題があります。
最後に、以下の本を紹介して終わりとします。
今回の記事で大幅に参考にさせてもらった本で、里親になりたいなら必読本です。
特に、P82のコラムの「高年齢児には年配の里親を」は濃い内容です。
また、以下の本もお勧めしておきます。
発達障害の人が里子には多いので、知識をつけておくべきです。
AI生成YouTubeを始めたこともお知らせしておきます。
(試しに1つの動画を載せておきます)
僕のYouTubeへは以下のリンクから飛べます。
https://www.youtube.com/channel/UCmikajHHXLoJm6zmevCYY1g
また、死とは何か?について、つまり死生観や医学についても知っておきたいところですね。
(興味がない人は飛ばしてください)
以下のことがこの本を読むと学べます。
| ・ | 体温が30℃を下回ると、意識を失って死の危険が高まり、20℃を下回ると、死に至る。 体温が42℃を超えると命に危険が及び、44℃を超えると死に至る。 |
| ・ | 体重の約60%は水分。 体の中の約60%の水分のうち、2%が失われると、強いのどの渇きを感じるようになり、4%以上なくなると、頭痛やふるえなどが起きる。 10%以上なくなると命の危険が生じ、20%以上で死に至る。 |
| ・ | 体重の7〜8%が血液。すべての血液量の20%以上が短時間で失われると血圧が下がり、皮膚が青白くなる、発汗が出る、脈が弱まり速くなる、ぐったりする、呼吸不全になるといった出血性ショックになる。 失血量が40%を超えると、死ぬ危険がある。 |
| ・ | 空気中の酸素の濃度はふつう21%。 酸素濃度18%までが体にとって安全な範囲。 16%を下回ると、頭痛や吐き気が起き、8%を下回ると数分で死ぬ。 |
| ・ | 死の三徴候とは、心拍の停止、呼吸の停止、瞳孔反応の消失である。 |
| ・ | 人体は体重の約98%が、酸素、炭素、水素、窒素、カルシウム、リンのたった6種類の元素でつくられている。 |
| ・ | 検視と検死と法医解剖の違い。 |
| ・ | 人が死を受け入れるまでには、「否認」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」の5段階のプロセスをたどる。 |
| ・ | 2005年には病院での死の割合が8割以上になった。(在宅死を希望する人は50%以上) |
| ・ | 基礎代謝の内訳は、おおまかにいうと、筋肉(骨格筋)が22%、脂肪組織が4%、肝臓が21%、脳が20%、心臓が9%、腎臓が8%、その他が16%。 |
以下の本も併せて読むと、医学系について理解が深まります。
ではこの辺で。(6738文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。





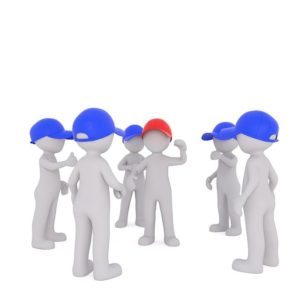




コメント