どうも、太陽です。(No72)
突然ですが、「頑張っても給料が上がらない理由は何か?」を皆さんは考えたことがありますか?
よく「今の会社が嫌なら転職しろ!」と言われますが、正論だと思いますか?
僕はひろゆきの動画を見る前は「正論だ」と思っていました。
ですが、ひろゆきの動画を見て、意見が変わりました。
個人の問題(転職など)以上に、「マクロな社会の問題が潜んでいる」と思ったからです。
このテーマに興味がある人は続きをお読みください。
1 日本とアメリカの平均年収と物価の伸びについてとアベノミクスの総括。
まず、背景知識・前提知識を抑えておきましょう。
| ・ | 日本の1990年の年収は約406万円から2020年は約424万円(約1.04倍の伸び) |
| ・ | アメリカの1990年の年収は約537万から2020年は約763万円(約1.42倍の伸び) |
(1ドル110円計算です)
1990年と比べて、アメリカの物価はほぼ2倍。 日本は10%程度の伸び。
つまり、アメリカの収入の伸びと物価の関係は、収入が30年間で1.42倍に増えましたが、物価は2倍。
日本は「30年間で収入がほとんど伸びず、物価もほぼ変わらない」とわかりました。
生活水準でいえば、アメリカは収入が30年間で1.42倍に増えましたが、物価は2倍だから、苦しくなっています。
日本は30年間で収入がほとんど伸びず、物価もほぼ変わらないで影響が少ないです。
ここで円高・円安問題、つまり、為替の問題が出てきます。
内外価格差の問題は「外国に出稼ぎに行ける」という影響があります。
現在であれば、アメリカで働けば給料が高く、そのドルを円に戻し、日本に戻れば豊かになります。
昔は発展途上国の人たちは日本に出稼ぎに行けば豊かになれましたが、今は安い日本になってしまいました。
つまり、生活水準という面でいえば、アメリカや日本など国内だけで完結してみれば、自国の収入と物価の上昇は差し迫った問題です。
買える量(生活水準)でいえば、アメリカも日本もそこまで変わらないかもしれません。
しかし、アメリカと日本で、それぞれ年収と物価があまりにも開いてしまうと、内外価格差が生じ、これが「出稼ぎができる」という状態につながります。
ちなみに、国と国との生活水準や生産性の違いを比較するためには、物価の違いなどさまざまな要因を考慮する必要があるのですが、その際に使われるマクロ経済分析の指標「購買力平価(PPP)」について、詳しく書かれた記事が以下です。
さて、アベノミクス(3本の矢。金融政策、財政政策、成長戦略)で円安を引き起こし、投資家に期待を持たせ、株価を上げた過去があります。
また、以下の記事のように、借金約1200兆円の利払い費がかさみ、破綻を恐れて、国債を日銀が大量に買い込み、長期金利を抑えたせいで、日米金利差が開き、「円安・物価高に進んだ」という背景もあります。
https://www.sankei.com/article/20231031-CTMDXEVA5NNB3J4GPMKBNXLYTE/
植田日銀、見通しの甘さ露呈 金利上昇、円安で2度目の政策修正
また、「長期金利の上昇容認は固定型住宅ローンや企業向け融資の金利上昇につながる可能性もある。金利の上昇は設備投資や消費の減少を招きかねない」と書かれており、その遠りでしょう。
一般的に好景気によるインフレ(物価上昇)局面の際は、金利を引き上げて景気過熱を抑える、それに対して不景気によるデフレ(物価下落)傾向になったら、「金利を下げて、経済を刺激し、景気を上向かせよう」とするのが基本です。
日本は景気が過熱しているわけでもないのに、金利引き上げを容認路線ですから、不景気に逆戻りの可能性もあり得ます。
さて、インフレはなかなか起こりませんでしたが、2022年ごろから悪い物価高が始まりました。
(原材料の輸入品の上昇と原油などのコストプッシュインフレのうちの資源インフレ。賃金の高騰による賃金インフレは起きていない)
インフレの種類(「コストプッシュインフレ」と「ディマンドプルインフレ」)についての詳しい説明は以下の記事を読んでください。
需要が高まり価格上昇が起こる現象を「ディマンドプルインフレ」と呼びますが、日本は円安政策で、輸出企業に価格面の優位性を築かせて、値段が高くても欲しいと思わせる戦略を取ってきませんでした。
iPod、iPhone、iPadなどのようなイノベーション商品開発力は日本は弱いです。
そして、3本の矢のうち、金融政策だけ機能し、財政政策と成長戦略は不発でした。
そもそも、円安誘導は輸出企業だけに有利で、しかも80円ぐらいから150円になっており、数量を売らなくても勝手に売り上げが上がる楽な仕組みです。
ちなみに、2011年10月につけた1ドル75円32銭が円高の戦後最高値です。
以下の記事を見れば一目瞭然ですが、アベノミクス以降、ずっと円安基調です。
https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2022/10/irepo221021/
ドル円相場の歴史~トレンド転換となった過去のイベントを整理する
このような円安基調のなかでも、東芝は2023年12月20日に上場廃止とのこと。
さて、トヨタなど一部の企業が円安で大儲けです。
以下の記事にもあります。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD2228Z0S3A021C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1698814888
トヨタ純利益過去最高の3.9兆円 24年3月、6割増に修正
工場が海外に移転する産業の空洞化へは一定の効果はあったでしょう。
(逆に、円安のおかげでTSMCが熊本に来ました)
また、投資家は「皆が期待するものあがる」という仕組みを熟知しており、「中身のないアベノミクスでも株価が上がると皆が予想すれば上がる」と分かっていました。
しかし、現実問題、成長戦略は機能しませんでしたが、それは当然です。
円安で大幅に下駄を履かせてもらった大企業は「生産性を上げる気になるか?」という話です。
現在、日本の株価が上がっているのは、アメリカが新興国から投資資金を引き揚げ(思ったより旨味がなかった)、その余剰投資金を以前から割安と言われていた日本株に一部振り向けただけだと予想します。
アベノミクスは果たしてちゃんと整合性がとれた計画だったのでしょうか?
円安がそもそも輸出大企業優遇であり、庶民は置いてけぼりです。
その輸出大企業はトヨタ(もともと、生産性高いうえに自民党と癒着)や大企業群であり、一部の大企業は崩壊しました。
円安で下駄を履かせてもらった大企業が生産性を上げる動機はありません。
そして、円安により、本来ならインフレを起こし、賃上げも実現し、好景気の循環を作りたかったのでしょう。
しかし、生産性向上という考えが抜け落ちていました。
また、円安により、インフレを起こし、国の借金を目減りさせることも考えていたでしょう。
加えて、「安い日本によって観光立国路線を目指していた」ことも読み取れます。
(コロナで一時、頓挫しましたが)
そこに、「外国人労働者が来なくなる」という発想はありませんでした。
では80円のままの円高政策で行くべきだったのでしょうか?
アベノミクスがなければ株価上昇は起こっていなかったでしょう。
(期待で上がっていましたが、その期待すらなかったからです)
では80円のままだったら、どこが困るのでしょうか?
輸出大企業です。
トヨタを中心に自動車産業を守り抜くくらいがメリットでしょうか?
そして、80円だったら、当然、観光立国は成り立ちません。
中国人の爆買いもないでしょう。しかし、外国人労働者は来ます。
庶民が今のような物価高で生活に喘ぐ可能性も下がったでしょう。
80円なら、iPhoneも買えました。輸入品を買いまくれました。外国旅行にも行けたでしょう。
年金生活者の老人大国日本であれば、資産運用も貯金が多いですし、アベノミクスのチャンスも逃した人が多かったので、物価が安いほうがいいのです。
まぁGPIFが株価上昇に乗じて、かなり儲けたのですが、いつまで続くのでしょうか?
また、80円の円高のままでも、輸出ではなく、内需向けにイノベーション製品を生み出し、儲ける方向性はなかったのでしょうか?
留学することすら苦しい時代になりました。
150円にする円安政策は必要だったのでしょうか?
ここは「議論の余地が大いにある」と思います。
ここまでの前提知識を基に、ほかの人が話さない「頑張っても給料が上がらない理由(マクロ編)」の本題に切り込んでいきます。
2 頑張っても給料が上がらない理由(マクロ編)
ひろゆきの以下の動画で話されていたことをまとめます。
(僕の解釈も含みます)
まず、「経団連って悪だ」と僕は理解しました。
自民党に献金を払って、産業別労働組合を作らせるのを妨害していたからです。
企業別労働組合だった韓国も法案を通して、産業別組合にして、実際に賃金が上がっています。
企業ごとのストライキをしても効果が弱いのです。
産業別労働組合だと一斉にストライキが行え、賃上げを認めざるを得ません。
外国ではそのようにして賃金が上がっていきました。
経団連が自分たちの都合で賃上げを妨害していて、自民党もそれに乗っかっています。
労働者の味方であるはずの連合は野党の立憲民主党から離れて、自民党にすり寄り始めました。
他の党も労働者の味方の党はいません。
日本では自民党がしきりに「賃上げだ」と言っていますが、その裏では賃上げに効果的な「産業別労働組合を認めない」という矛盾した行動をとっています。
「外国ってやけにストライキが多いな」と僕は以前から感じていました。
そして、「なぜ日本では起きないのか?」不思議でした。
「民度や治安の問題か」と思っていました。
しかし 「産業別労働組合が法律で規制されていた」とは初耳でした。
これが「大々的にメディアで話題にすらなったことがない」と記憶しています。
労働者が団結してストライキを行えなければ、そりゃ企業側が強いから、賃上げにつながりません。
日本ではよく「嫌だったら、転職しろ」と言われますが、外国ではストライキする権利があったのです。
日本の労働者は騙されていました。
経団連と自民党とこのテーマを報道しないマスコミに。
企業別労働組合の日本はある意味で言えば、メンバーシップ型雇用の日本そのものです。
会社に愛着がある前提で、外資のように関係がドライではありません。
外国が産業別労働組合でストライキをできるのはドライだからです。
また、転職市場が整っており、「嫌ならほかの会社に移ればいいや精神」があり、つまりドライな関係です。
「日本のメンバーシップ型雇用、転職市場が整っていない」などダメな部分が全部出て、「賃上げにつながらなった」と推測します。
外国のように、ジョブ型で転職市場が整い、ドライな関係で産業別労働組合があり、「ストライキで賃上げする」という構図がありませんでした。
じゃあ、労働者側の訴えじゃなく、企業側の善意で賃上げをすればいいのですが、なされませんでした。
大企業は内部留保を溜め込み、それは将来への心配・不安からです。
日本の偉い側は、労働者を使い倒し、「家族・仲間だ!」と見せかけながら、実は搾取していました。
TV局もジャニーズ問題はイギリスの圧力があったから、ようやく動いたわけで、それまでは見て見ぬ振りでした。
しかも、ジャニーズ事務所は奴隷契約をしていました。
(ギャラの75%がピンハネ)
偉い側の善意なんて期待しても無駄なのです。
労働者が被害を訴えないと変わりません。
産業別労働組合がないと企業や偉い人は動きません。
産業別労働組合を規制してきたのが、都合がよかった大企業中心の経団連です。
そして、経団連に献金を受けてきた自民党です。
自民党はアベノミクスのときもそうでしたが、ずっと大企業優遇でした。
庶民や中小の労働者や老人は置いてけぼりでした。
(物価高もそうですし、賃上げもないですし、株価上昇の旨味なし)
そして、自民党=経団連(大企業群)=TV局などメディア=芸能事務所などがグルになって、支配を続けてきました。
全て、彼らに都合がよく、有利になるような政策ばかり打たれてきました。
その結果が今です。
結局、「誰のための政治か?」ということは政策を見れば一目瞭然なのです。
そんな状況の中、2023年10月29日に維新の会は「企業献金を全面禁止」すると発表しました。
「自民党ができないことをやろう!」というわけで、産業別労働組合を認めるつもりなのでしょうかね。
立件民主党は2023年8月時点で「企業団体献金の禁止にチャレンジしなければ政治は腐る」と主張しています。
自民党の矛盾が明らかになったのではないでしょうか?
(大企業=TV局などのメディア=芸能事務所など全部がグルになり、自分たちに有利になるように自民党と癒着していたのです)
「賃上げが起きない!」と盛んに騒いでいる一方、それは自分たちが規制したせいなのを無視しているのです。
大企業にとって、ストライキなんて起きたら、嫌ですからね。
もちろん、日本の治安が若干、悪化する可能性も残りますが、偉い人の善意なんて期待しても無駄ですので、戦う権利はあるべきなのです。
「嫌なら転職しろ」の決まり文句には、「外国では産業別労働組合が認められており、ストライキできるが、日本ではできない。外国よりは不利だ」と反論できるでしょう。
最後に、以下の記事でも、ストライキを起こせなかった日本人の気質や制度が賃金が上がらなかった理由の一つだと書かれています。
ではこの辺で。(6076文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
逆内外価格差を考える(前編)
~30年前の内外価格差の議論と失われた30年~
https://financial-field.com/income/entry-130760
失われた30年 日本人の年収はなぜ上がらないのか

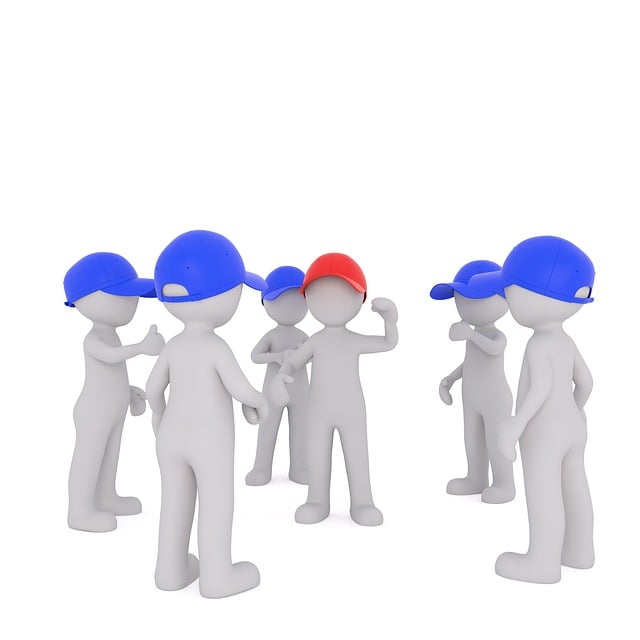








コメント