どうも、太陽です。(No8)
突然ですが、メンタリストDaiGoの質疑応答の動画で、以下のような話がなされていました。
(僕の解釈も含みます)
【質疑応答】相手にする価値がない人間関係の切り方
フランスは労働者の権利がかなり守られている国で、失業率が20%です。
三ヶ月に1回面接に行き、証明書をもらえれば、国から永遠に失業保険がもらえます。
家賃が半額になり、お金が毎月もらえますが、最低限の暮らしです。
国民は最低限の暮らしは嫌なので、現金がもらえる日雇いのバイトをし、バーとかで遊びます。
シェフは積み重ねの職業で大変なのに、そういう人達より給料が安くなります。
真面目に働くよりも、失業手当をもらって日雇いのバイトをしたほうがよい生活ができるのです。
真面目に働くのがバカらしいとなります。
この負の連鎖が起きて、失業率が20%超えなのです。
また、違う話ですが、リモートワークになって収益が過去最高益になった会社があります。
コロナで打撃を受けたはずなのに、過去最高益なのです。
この会社の社長が言うには「いない方が仕事がはかどる社員がいることが明らかになった」ということでした。
今まで会社で有能な人がやらなくていい仕事を「無能な社員のせいでやっていた」などがあったのです。
で、それがなくなり、有能な社員は力を発揮できますし、「無能な社員は邪魔をできなくなった」ということです。
ここから、「ベーシックインカムはありかも?」とその社長は思ったと言います。
ほとんどの人は暮らしていければいいのであって、そういう人を無理に働かせると、有能な人の足を引っ張るのです。
で、「そういう人をベーシックインカムであまり働かせなければ社会の生産性は上がるかも」という話です。
現場で有能な社員が働いていて、上の上司などが逆に無茶な指示などをして、生産性を下げているケースもあります。
そういう無能な上司などはいない方がいいのです。以上、ここまで。
日本維新の会はベーシックインカムを推しており、ひろゆきも選挙で票を入れました。
「そこまでして、ベーシックインカムを導入したいのか!」と驚きでした。
今回は、ひろゆきが激推しするベーシックインカムが実施される際に起こる、僕が想像しうる「思考実験をしてみたい」と思います。
議論のたたき台となれば、と思います。
興味がある人は続きをお読み下さい。
PART1です。
1 ベーシックインカム構想の思考実験。
いきなりですが、この月7万円を国民全員に配る案が実現されていく過程において、「どういう問題が発生するのか、思考実験してみたい」と思います。
いきなり、月7万円が配られるとなり、「国民の世代ごとに以下の反応・行動が見られるようになる」と思います。
若者世代。(10代〜20代)
夢を追う者と、最低限生活をしていければいいとフランス人のようにバイト生活をする者に分かれます。
(無気力な夢がない人も世の中には案外います)
夢を追う者にとって、月7万円の確保はありがたく、大きな支援となります。
そして、最低限のバイトだけして、後は夢を追う活動に時間を割くようになるでしょう。
夢ばかり追い、現実を見なくなり、「大企業や公務員などに手堅く就職して我慢する」という道を選ばなくなる若者が続出する懸念もあります。
野心のある層が多ければいいのですが、大概、野心のある人の方が少ないので、堕落の道を辿る人が多いと予想します。
また、夢の職業というのはパイが限られており、大半は挫折になります。
ですので、「挫折した若者がどこに行くのか?問題」はあります。
(結局、「バイトでいいやの人」になる可能性もあります)
中年世代。(30代〜50代)
子供がいる世帯は、暮らしが楽になります。
30代では「子供をもっと産もう」という動機づけになるかもしれません。
夢を追う中年もいれば、「バイト生活を続ける」という無気力な中年もいるでしょう。
バイト生活の若者・中年が多くなるのであれば、そりゃ、ひろゆきは「安い給料でバイトしてくれる外国人労働者受け入れに反対する」に決まっています。
(農業のバイトをする人は少ないので、農業まで反対する理由はないと思いますけどね)
老人世代。(60代以上)
急に、月7万円に減額されたので、暮らしが成り立つか、不明になります。
かといって、今まで年金生活で済んでいたのが、高齢になってバイト生活は大変になります。
資産や貯金を切り崩す生活になる老人世代も多くなるでしょう。
生活保護をもらっていた高齢世代は、働かなくてはいけなくなります。
(元々、働けなかった人達もいると思うので、そういう人はホームレスになるのでしょうか)
ホームレスがかなりあふれる社会になります。
(しかも老人ばかり)
番外編として、若くして病気などで働けない人達もいて、そういう人達もホームレスになります。
ホームレス対策として、国が集合住宅などを借り上げて、提供します。
(家賃はタダになり、その上に月7万円がもらえます)
そこに老人ホームレスや働けない若者層が住み込み、僕の集合住宅案が実現化します。
これと似た案の本が「年寄りは集まって住め 〜幸福長寿の新・方程式」でして、2021年8月30日に発売されていますが、実は僕の方が記事が先だったのです。
(違うブログで先に出しており、こちらに移転させたので、僕のほうが遅く見えていますけどね)
話を戻します。
ただし、「空き家も同時にかなり増える」と思われるので、「その後始末をどうするか?」です。
(若者がほぼ無料で引き継ぐ?)
集合住宅を借り上げる、買う資金が別に国にかかり、けっこうな負担となるのが弱点です。
大量の老人ホームレスが湧き出てくるので、与党に対し、「弱者切り捨てか!」と猛反発が出ます。
そして、仮に集合住宅を確保しても、「姥捨て場か?」と批判を浴びます。
与党は当然、ベーシックインカム案を実行できるわけがなく、実行されるとしても、老人世代がほとんど死んだ20年後とかになり、不透明になります。
以上です。
「世代ごとに、またはどういう層がどういう反応・行動をするか?」予想をすると、「ベーシックインカムの妥当性が見えてくる」と感じます。
若者で月7万円増えたら、こういう反応・行動をするだろうな、中年ならこうだろうな、老人ならこうだろうな、さらに細かくセグメンテーション・ターゲティングすることも可能でしょう。
老人世代の猛反発は必至です。
さらに若者の堕落化の懸念もある上に、「安定より夢追い人」を増やすので、大企業や公務員志向がかなり薄れるかもしれません。
(フランスのように失業率が上がったり、フリーター組が増加するかもしれません)
生活の安定という意味では「失業はしないだろう」という安心感が生まれ、不安な人が多い日本人には救いです。
ですが、同時に堕落への道でもあり、「ベーシックインカム制度が存続できるのか?」問題も起きそうです。
急に「ベーシックインカムは失敗でした!存続できません。打ち切りです!」となると「また元の制度に戻すのか?」となります。
社会実験としてはかなり大冒険になります。
ですので、仮に実施するとしたら、外国の事例を参考にしたり、「一律ではなく、どこかの県だけで試しにやってみる!」という実験をするのが「正解だ」と僕は思います。
「東京都だけやってみる」とかですね。
ちなみに、僕は無理にベーシックインカムを実現化しなくても良い派です。
つまり、「見込みのある層に資金を配り、生活保護を残しつつ、集合住宅案などで経費削減できればいいかな」という思いです。
でも、集合住宅案はホームレスになった層がたくさんいた方が現実化しやすいんですよね。
また、一律に国民全員に月7万円だと、無駄打ちが極めて多くなります。
ただし、「少子化の歯止めになる」と予想します。
「家族が多い方がお金を多くもらえるから」ですね。
ホームレスが大量に発生したら、相当なインパクトがあり、日本だったら大問題になりますね。
これをひろゆきは起こそうというのですから、ある意味で狂った政策です。
ですが、これくらい狂った政策をしないと日本はもうダメなのかもしれません。
ちなみに、「生活保護世帯は今後、急増する」と思われます。
いずれ「生活保護でカバーできない、限界だ!」となり、ベーシックインカム待望論が出てくる可能性はあります。
ひろゆきはYouTube動画で盛んに「足を折ってでも、生活保護を受給しろ!」と言っています。
それは、生活保護者が増えれば増えるほど、ベーシックインカム実現が近づくからなのです。
ひろゆきの主張は首尾一貫しています。
ベーシックインカム実現のために、外国人労働者反対や、生活保護受給の勧め活動をしているのです。
思考実験として、思いついたのは上記の内容ですが、何か他に考えが浮かんだら、追記するかもしれません。
最後に、思考実験の初心者用の本として、以下の本があります。
「この1冊で「考える力」が面白いほど鍛えられる!思考実験BEST50」
あのアインシュタインも思考実験オタクとして有名です。
本の内容を一部、紹介します。
最大多数の最大幸福を目指す功利主義の考え方には、「最大救命原則」と「社会秩序原則」があります。
「最大救命原則」とは、もっとも多くの人を救うことを考えて、資源を配分するという考え方です。
「社会秩序原則」は、社会秩序を守る人に優先的に資源を配る考え方です。
迷信行動(因果関係のない2つの行動に因果関係をつくる行動)を起こしやすいグループとして、ギャンブラーと運動選手がいます。
脳の報酬系が活発に活動する一方で、自分の行動を振り返って、検証するような行動が極端に減るので、ギャンブラーの場合なら、リスクを取りすぎてしまいます。
脳の中で勝手に因果関係を設定して、自分に都合の良いように解釈する認知のかたよりの一つに「ギャンブラーの誤謬」があります。
黒が9回連続して出た後に、10回目のルーレットで「黒が出るか、赤がでるか」、皆さんはどっちだと思いますか?
「さすがにそろそろ赤が出るだろう」と思いがちですが、10回目のルーレットでも黒が出るか、赤が出るかの確率は2分の1なのです。
9回連続で黒が出る確率は512分の1で、珍しいのですが、過去の結果は未来に影響しないのです。
確率はルーレットを行う回数が少ないと、本来の2分の1からかけ離れた結果が出る場合があります。
これを「少数の法則」と呼びます。
こうした科学的な法則を無視した過度な期待や思い込みが、ギャンブラーの誤謬を引き起こします。
一生懸命働いた後に飲むビールはとてもおいしいと感じる人が多いでしょう。
ですが、これは辛い努力をしたほうが、得られる報酬が大きいという錯覚です。
つまり、損をすればするほど、得られる報酬が大きいと思うことでもあります。
苦労したほうが得られる結果が大きいという因果関係を見出してしまいますが、世の中は常にそうじゃありませんよね?
思考実験の訓練をしたい方は読んでみてはいかがでしょうか?
ではこの辺で。(3644文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。





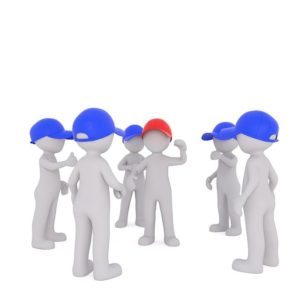




コメント