どうも、太陽です。(No37)
突然ですが、「日本の転職市場は変わるのか?」というテーマで書いていきます。
このテーマについて「真剣に自分事として考えている人がどれだけいるか?」不明ですが、「気になる!」という人はぜひ、続きをお読み下さい。
1 僕が考える日本の転職市場が変わるのか?についての意見。
いきなりですが、日本の「終身雇用制度」「年功序列」「新卒一括採用」は制度疲労を起こし、企業自体がこの制度を維持できなくなっています。
ところで、日本は以下の制度を構築してきました。
| 1 | 終身雇用を前提としたメンバーシップ型雇用形態。 (会社が家族みたいな形) |
| 2 | 職務や勤務地を限定しない新卒一括採用。 |
| 3 | 社内で色々な仕事やポストを経験させる制度。 (新卒をとことん使い倒すし、合わない仕事でも配置転換し、柔軟に対処する) |
| 4 | 職務が明確じゃなく、評価基準も曖昧なので、給与は年功序列が基本。 |
このような中で、社員は専門性が磨かれず、プロ意識に欠け、生産性を下げていました。
そこで浮上したのが、早期退職や退職勧告ですが、問題が生じました。
辞めて欲しくない人材が退職し、辞めてほしい人材が会社に残る問題です。
優秀な人材ほど転職の誘いが来て、転職してしまうのです。
彼らを囲いこもうとしても、限界がありました。
しかも合理化が終わり、攻めのIT人材を採用しようとしても、既存の給与体系では彼らの雇用条件を満たせず、採用時のハードルも高くなってしまいます。
そこで、タニタという会社が採用したのが、社員を雇用事業主にする作戦です。
個人事業主を希望する社員は会社に申し出て、「本人が納得すれば退職して個人事業主になる」という内容です。
(選択制なので、独立を強要するものではありません)
詳しい仕組みについては「不況を乗り切るマーケティング図鑑」という本をお読み下さい。
2019年10月現在で22人が個人事業主になっています。
個人事業主になった社員の比率は全社員210人のうち、1割を越えました。
広告代理店の電通も、社員を個人事業主に転換させる制度を採用していますね。
個人事業主(自営業)といえば、「フリーランスか?」と思う人もいるでしょうが、厳密な区別があります。
フリーランスは単発の仕事ごとに契約を結び、仕事をして報酬を得る人です。
(傭兵的な働き方)
「期間を定めて契約を結び、案件ごとに発注書を受け取り、仕事に着手する人」のことを指します。
例。ITエンジニア、カメラマン、デザイナー、ライター。
会社や勤務時間に縛られず、自分の得意分野を生かして仕事ができます。
一方、個人事業主(自営業)は「企業に属さず、個人で事業を営んでいる人」のことをいいます。
個人事業主と自営業は基本的に同じで、税務上の所得区分の言い方で、個人事業主と呼んでいるだけです。
例。レストランなどの飲食店、ヘアサロン、生花店、建築など。
アメリカではフリーランスの人口は5700万人であり、アメリカの労働力の35%を占めます。
すでにアメリカ人の3人に1人以上がフリーランスなのです。
フリーランサーの職種として多いのが「プログラミング」「マーケティング」「IT」「ビジネスコンサルティング」の専門家であり、全体の45%を占めます。
その後に続くのが専門スキルを必要としない「犬の散歩、ライドシェアリング、個人タスク」「販売(eBayやAirbnb)」「その他アクティビティ」となっています。
日本の2019年の平均雇用者数は5600万人(役員を除く)で、そのうち正規の職員・従業員数は3494万人であり、非正規の職員・従業員数は2165万人です。
また、小規模事業者は、企業数325万2000社、従業員数1127万人(平成26年)です。
ランサーズのフリーランスの調査によると、常時雇用されていて副業として仕事を受けている副業系隙間ワーカーが409万人(平均年収63万円)で全体の40%を占めています。
雇用形態に関係なく2社以上の企業と契約ベースで仕事をする複業系パラレルワーカーが281万人(この仕事だけで生活しているのは11%で、17%は年収400万円以上ある)で全体の27%を占めます。
特定の勤務先はなく独立したプロフェッショナルの自由業系フリーワーカーが56万人(この仕事だけで生活しているのは42%で、14%は年収400万円以上ある)で全体の5%を占めます。
そして個人事業主とひとりで法人を経営しているオーナーなど自営業系独立オーナーが289万人(この仕事だけで生活しているのは64%で、37%は年収400万円以上ある)で全体の28%を占めます。
この数字からわかるのは、日本でフリーランスと呼ばれる働き方は、本業とは別に副業を行う人が40%もいて、「アメリカのプロフェッショナル的な働き方(全体の45%)とは違う」ということです。
日本の1年間の転職者(2019年)は329万人、雇用の流動性の比率にすると労働人口の4.9%に過ぎません。
男性が152万人で4.1%、女性が177万人で6.0%という状況です。
世界的には、転職経験のない人の割合は日本とドイツが55%前後で最も高いです。
次いで韓国が40.3%、スウェーデンが31.8%、アメリカは最も低く27.3%となっており、「アメリカのフリーランス大国の傾向とも合致している」と思われます。
最適な仕事に就いていて、生産性が高ければ流動性は低くても問題ありません。
ですが、生産性の高い業種や会社に「日本の場合、移動していない」と思われます。
日本での再就職先を探す方法は、エージェントの活用・求人広告の閲覧・リファラル採用(社員に人材を紹介してもらう方法)・ハローワークでの相談など、方法が限られていました。
一方、アメリカでは、ネットワークづくりが日常的になっています。
アメリカでは企業からの求人の7割ほどは公募されず、人脈を通じて決まるのです。
(これが効率がいい方法なのです)
求職者は知り合いを通じて企業を紹介してもらいます。
中途採用だけでなく、新卒でも、入社したい業界や分野の人とは、日頃からソーシャルメディアを通じて積極的にネットワークづくりに取り組む国がアメリカです。
シリコンバレーでビジネス特化型SNSがあり、その名は「LinkedIn(リンクトイン)」です。
登録メンバーは6億9000万人を超え、日本では200万人以上が登録しています。
(2020年7月現在。同社は2016年12月にMicrosoftによって262億ドルで買収されています)
ビジネスパーソンがLinkedInを使うメリットは、以下があります。
| 1 | ビジネス情報を「タイムライン」から収集できる。 |
| 2 | ビジネスのネットワークづくり。 |
| 3 | 自身のプロフィールを掲載し、自分をアピールできる。 |
| 4 | 興味のある企業とつながり、企業情報を入手できる。 |
| 5 | 転職や就職活動に活用できる。 |
| 6 | LinkedInラーニングというオンライン教育システムがあり、受講が終了するとプロフィールに掲載できる。 |
企業がLinkedInを活用するメリットは以下です。
| 1 | 「会社ページ」を使うと、世界に向けて自社のブランディングができる。 |
| 2 | 転職潜在層に直接アピールできる。 |
また、アメリカにはさらに驚くべきサービスを提供する企業があります。
AIによるヘッドハンティングサービス提供会社のscouty(現LAPRAS(ラプラス))です。
LAPRASは、インターネット上に公開されているエンジニアのSNSやブログなどの情報をシステムが収集し、「技術力、ビジネス力、影響力」という3つのスコアを算出します。
そして、個人のスキルや志向性、活動内容などを含めた個人のプロフィールページをAIが自動生成します。
これらのデータを元に、エンジニアと企業との最適なマッチングを実現するのです。
採用候補者のプロフィールページは、クライアント企業と候補者の両者が閲覧できます。
転職市場に出てこない転職潜在層にアプローチできます。
このサービスの特徴は、転職候補者が自分のことを登録する前に、自身のプロフィール情報が既に作成されている点です。
自分以上に自分のことを知っている存在がRAPRASです。
(個人情報をネット上に怖くてアップできない問題が日本なら起こりそうです)
また候補者が転職活動を開始する前に、自分に興味を持っている企業を事前に把握でき、そこから転職活動を開始できるメリットもあります。
加えて、「技術力・ビジネス力・影響力」の3つのスコアは詳細を閲覧できるので、転職を考えていない人にも、自分の現状と評価を確認できます。
(日本じゃ考えられないシステムです)
ネット上に公開されている情報から、候補者のポートフォリオは作られます。
主に、エンジニア職種に特化した採用サービスで実績があります。
(ポートフォリオ数は150万件を超えています)
LAPRASに関する詳しい情報は「不況を乗り切るマーケティング図鑑」をお読み下さい。
アメリカでは名刺の時代は終わり、「ネット上で自分のプロフィールが検索される時代が始まっています」が、日本にも到来するのでしょうか?
僕の予想としては、以下のことがわかります。
アメリカのプロフェッショナル的フリーランサーが全体の45%であり、職種も「プログラミング、コンサル」など、在宅ワークもできそうですし、「ネット上から収集し、データ化・見える化しやすい技能」ということです。
アメリカは製造業から、金融・IT産業に転換し、さらに昔から経営(コンサルティング)も強い国です。
日本はIT大国でも金融大国でもなく、経営(コンサルティング)も発達しておらず、製造業の比率もまだ高いのです。
日本の転職市場はまだまだ整っておらず、他社に転職しづらい状態です。
だからこそ、日本独自?のタニタや電通のような「個人事業主に転換するやり方」を採っていると思われます。
日本企業は、今後、優秀な人材を自社とつながらせつつ、個人事業主契約にし、「筋肉質な体質にする気だ」と思われます。
一方で、テレワークもできず、お荷物的社員は会社で強制力を持って働かせるのです。
または日本で発達した
「常時雇用されていて副業として仕事を受けている副業系隙間ワーカー」
「雇用形態に関係なく2社以上の企業と契約ベースで仕事をする複業系パラレルワーカー」
の働き方もさせて、自社で全て抱え込み、責任を取るというやり方をしなくなるのです。
(つまり、副業、複業もやらせるのです)
日本では解雇規制が強く、容易に解雇できないので、このようなやり方を採っています。
優秀な人には「個人事業主でもいいよ」(ただし、「自社となるべく契約してね」)と言い、お荷物社員には「副業、複業をしろ」と迫るのです。
日本ではアメリカのような完全なプロフェッショナル的なフリーランサーはまだまだ多数派にならないでしょう。
しかし、徐々に大企業の体力も持たなくなり、フリーランス、複業・複業的な働き方を強いてくるはずです。
日本の個人事業主やフリーランスの立場は弱く、「住宅や車のローンが容易に組めない点、クレジットカードがつくれない」など不利な扱いを受けます。
また、企業の正社員から、個人事業主やフリーランスに転向した人の最大の問題は顧客の開拓です。
現状の方法としては、これまで築いてきた人的つながりを頼るか、SNSを使ってアピールするしかなかったのです。
ですが、ここで登場したのが「クラウドワークス」や「ランサーズ」などのサービスです。
しかし、高度な専門性と実績を備えていないと、安く買い叩かれます。
普通の人は、受注を増やしたいために、報酬を下げてエントリーし、依頼主も安価な人材を選ぶのです。
フリーランス向けの仕事を紹介するフリーランスエージェントと呼ばれるサービス会社があります。
IT系エンジニア・デザイナー・クリエイターならレバテック、ITエンジニア向けギークスジョブもあります。
転職市場が日本ではなかなか整わないのですし、まったくの人脈なしの人にとっては辛いのが日本です。
ランサーズやクラウドワークスでも安く買い叩かれます。
だからこそ、日本では「新卒切符を使い、大企業などに入る」という敷かれたレールから降りるのが怖い人が多いのです。
アメリカではいろいろなサービスが流行っており、転職が当たり前、プロフェッショナル的フリーランサーも多いです。
ですので、Clubhouseでも人気なのがビル・ゲイツやイーロンマスクになりますが、日本では起業家系は少なく、芸能人になるのです。
「日本の転職市場が変わるのか?」といったら、「日本独自のやり方で徐々に変わっていく」というのが僕の見立てです。
上記で延べたように徐々に変わってくしか、やり方がないのでしょう。
(解雇規制があるので)
加えて、以下の記事を貼っておきます。
https://news.mynavi.jp/article/20210421-1874929/
電通による「社員の個人事業主化」という働き方、メリットとデメリットを解説
この記事によると、タニタと電通の個人事業主推進策による、個人事業主のメリットとデメリットが詳細に書かれています。
個人事業主は僕が思う「「できる人」が選ぶ」というより、「自由になりたいなどのメリットを感じる人が選ぶ」モノのようです。
「会社に残り続けて自由がなくなるけど待遇が比較的良いか(副業推進により、企業の負担は減らす)」、「自由になるけど待遇は悪くなり、強者しかなれない道になるか(会社側の負担は減る)」、ということなのでどちらにせよ、会社側に都合がいい仕組みのようです。
2 SOW@新作出すよ、さんのインボイス制度についてのツイート。
日本ではフリーランスがかなりの少数派なことで「選挙に影響がない」と与党が考えたのか何なのか知りませんが、フリーランスにとって不利なインボイス制度を導入しようとしています。
以下、SOW@新作出すよ、さんのツイートを貼りますので、読んでみてください。
インボイス制度って、要は今まで免除していた個人事業者からも税金をかっぱぐってことなんだが、それだけ聞くと「免除されてたのか」「ずるい」とか思うかもだが、違うの、実態逆なの。
個人事業者って、個人でもあり事業者なの。
同じ手取りなら、個人事業者のほうが、倍近く払っているの。
いま現在も。
ここらへん計算ややこしくなるんだが、個人事業者ってのは、全部自分で揃えなきゃいけないの。
仕入れも加工も販売も販促も営業も宣伝も運送も、事務所も光熱費も備品も通信費も、全て自分で賄うの。
その全てで、消費税が発生しているの。
その上で、残った儲けが、利益となるのだが、そこからさらに税金や保険料などが差っ引かれ、だいたい、売上の1/3あったら多い方というくらいの分が、手取りなの。
その手取りで生活して、その生活費に、勤め人と同じように消費税かかかるの。
フリーランスが、一般の勤め人の倍稼いで、ようやく同じって言われるのはそういうとこなの。
さらに言えば、個人事業者は基本生活が不安定なの、さらに国保だから、老後の貯蓄が倍必要なの。
保険料も年金も全額払いなの。基本レギュレーションが圧倒的不利なの。
そういった事情があったので、「売上一千万以下の事業者」を免除していたのは、ただでさえ負担の不公平がある消費税で、厳密に適応していたらマジでヤバいという判断なの。
それを事実上廃止にしようとしているわけね。
完全な弱い者いじめなのよ、これ。
経済政策に置いて、大企業と小規模事業者、どっちを保護するかと言うと、小さい方を守るのが原則なの。
人道上の都合とかじゃなくて、そうしないと大企業一極集中が起こって、他の選択肢がなくなるの。
小さな事業者がやっていけなくなり、大企業が一人勝ち状態になると、競争相手がいなくなるので、大企業側は、労働者を逃がす危険がなくなるため、雇用環境がどんどん悪くなるの。
要は、給料削って、たくさん働かせ、保障はしないという状態ね。
労働者は逃げたくても、他に働くところがない以上、我慢するしかなくなるの、ブラック化がどんどん進み、食っていくにも難しいレベルになる。
「富の偏在」が制御不可能のレベルで加速してしまう。
これとおなじことがあったの。百年前の日本。
個人事業者である自営農家の生活がどんどん不利になった結果、大地主に吸収され、農村の小作人化が進んだ。
その結果、生きていくことも苦しくなった農家は、娘を売ったり、老人を口減らしたり、挙げ句に借金から逃れて離農して、都市部に流れ込みスラム化したの。
その頃になるともう、政府もどうしていいかわからず、場当たり的な対応しかできなくなるの。
そんな中、なんとかせんとと考え、暴走した青年将校たちが起こした事件が、5・15事件であり、226事件なの。
まぁここまではさすがに大げさと言われるかも知れないが、国内の個人事業者、それも一千万以下でやっている者は、2百万を超すと言われている。
その殆どが、ギリギリのラインだ。
なにせ二十年デフレが続いたので、どこも皆薄利多売のカツカツでやっているのだ。
そこにさらにこのインボイス制度が加われば、一般的なサラリーマン世帯に比べ、倍近い負担となる。
二ヶ月分の収入を失う者もいる。
なにせ全てが小規模事業者なのだから。
生活できなくなるもの、万単位で事業をたたまざるを得ない者が続出するだろう。
時代の逆行にもほどがあるのだ。
転職市場も整っておらず、副業・複業もやりづらく、さらにフリーランスになると不利になり、逃げ場のない日本においては、大企業などにしがみつくしかなく、まさに「日本はオワコン」という状態です。
与党はいったい何をしたいのでしょうか?
「小中高で起業家精神を教える」ということですが、フリーランスにここまで不利になる税制を作っておいて、起業家精神とは笑わせます。
さて、以下、僕が今回の記事を書く上で、かなり参考にさせていただいた本を紹介し、短文書評を書きます。
「不況を乗り切るマーケティング図鑑」
4点。
僕のビジネスの企画・発想のアイデアとしてかなり参考になった本。
この本を読んだら、アイデアが次々に浮かび、個人的に星0.5点を追加した。
この本を活かせるか、活かせないかも読者次第。
不況期の乗り切り方としても参考になるので、企業の経営者は特に必読であろう。
買い推奨。
この本の内容をつぎはぎし、「日本の転職市場は変わるのか?」というテーマでまとめ直し、さらに追加部分を加えたら、今回の記事が出来上がりました。
「この本さまさま」なのです。
「良書を活かせるか、活かせないか」はその人次第です。
ではこの辺で。(7725文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。





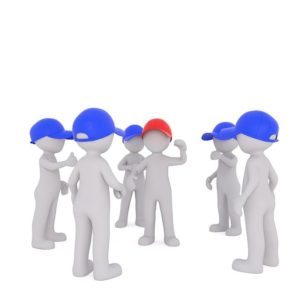




コメント