どうも、太陽です。(No4)
突然ですが、前回の記事が以下です。

高齢化問題の画期的な解決策「高齢化問題は他人事ではない、深刻な社会問題である2 追加編」
前回の記事で、以下の指摘をしました。
高齢の貧困者、氷河期世代が貧困者に陥ること、ロスジェネ単身女性も貧困者に陥ること、など「総生活保護者時代か!?」と思われそうなほど、弱者が日本に増える予測です。
僕の解決策は、「集合住宅で集まって住めば老老介護などの解消・効率化、食事共有などコスト大幅削減が可能だというモノ」でした。
で、日本の少子高齢化・低成長時代を考えると、「コストの徹底的な削減が一番確実な政策だ」と思ったので提言しました。
これと似た案の本が「年寄りは集まって住め 〜幸福長寿の新・方程式」でして、2021年8月30日に発売されていますが、実は僕の方が記事が先だったのです。
(違うブログで先に出しており、こちらに移転させたので、僕のほうが遅く見えていますけどね)
話を戻します。
しかし、日本では住宅がかなり余っており、空き家問題も言われていましたが、住宅の耐用年数が思ったよりも短いのです。
そして、「将来的に住宅の供給問題・構造問題はどうなるのか?計画して建てるべきだな」と感じました。
ですが、政府が採ろうとしている政策は住宅手当です。
なぜなら「民間や国民の意思決定に政府がそこまで関与することができないからだ」と思われます。
集合住宅に住みたい人が増えればいいのですが、持ち家信仰が地方ではまだあります。
さらに国民1人1人の住宅選びを操作できるわけでもありません。
ですから、「住宅手当(家賃補助)を出して、住む場所確保などの支援を金銭的にする」という形に落ち着いたのでしょう。
この話題について、書いていきますので、興味がある人は続きをお読み下さい。
1 記事からの引用・まとめ。
いきなりですが、以下の記事から、引用・まとめをします。(2021年の記事)
https://www.businessinsider.jp/post-244966
なぜ衆院選で「家賃補助」が争点になったのか。各党の政策を徹底比較
立憲民主党。
枝野幸男代表は「持ち家重視の日本の住宅政策を転換する」といいました。
さらに、低所得世帯や一人暮らしの学生へ向けて「家賃補助」を公約に掲げています。
日本共産党。
「住まいは人権」を掲げ、民間賃貸住宅の家賃補助の創設や、民間賃貸住宅を政府が借り上げる公営住宅などの支援策を掲げています。
日本共産党の主張は、僕の「集合住宅案に近い」ですね。
社民党と公明党は、コロナ禍で対象が拡大した「住居確保給付金」の恒久化・拡大を掲げています。
日本維新の会は、子育てバウチャーを導入し、その用途の一つとして子育て世代向けの住宅利用を掲げています。
自民党は「住宅ローン減税をはじめとする、住宅投資促進策を確実に実施」としていますが、公的な家賃補助の導入には言及していません。
日本には、まだ政府による住宅手当は存在しなく、その理由として、以下の2点があります。
| 1 | 今までは社宅や企業の家賃補助が住宅手当の役割を担っていたこと |
| 2 | 政府による住宅政策は主に住宅ローン減税など「持ち家」を促すものが中心だったこと |
上記の2点は、「終身雇用・年功序列」の日本企業の時代には適していました。
政府による住宅手当がなくても何とかなりました。
しかし、多くの企業は家賃補助をする余裕がなくなりました。
しかも、そもそも非正規雇用であったり、失業した人であればその恩恵は受けられず、政策の転換が必要になった背景があります。
コロナ禍で、「住居確保給付金」への2020年度の新規支給決定数は、全国で前年度の34倍に当たる13万5000件となり、住宅不安が加速していることが分かります。
さて、賃上げをするには、雇用の流動化が必要です。
(橋下徹氏も本で言っていました)
労働市場の硬直化により、衰退産業から成長産業へ人が移らなくなります。
であれば、生産性が落ち、そうなると賃金が上がらなくなります。
しかし、雇用が流動化すると、失業率が上がり、生活に困窮する人が増えるリスクがあります。
そこで、セーフティネットとして住宅手当が必要なのです。以上、ここまで。
住宅手当が必要なのは分かります。
ですが、「雇用の流動化(生産性を上げ、賃金を上げるため。だけど失業率も上げるリスク)とセットで語られる背景は斬新だ」と思いました。
僕の案では、将来的に「総生活保護者時代」と言われそうなほど、弱者が増えるので、徹底的なコスト削減のための集合住宅案でした。
ですが、民間に介入できない限界から、「住宅手当になった」と思っていましたので。
さて、以下の記事では、都道府県別の家賃が載っています。
https://gentosha-go.com/articles/-/38286
都道府県別家賃・間代ランキング
1位の東京がダントツで、1ヶ月8万1001円です。
以下、2位神奈川、3位埼玉、4位千葉と続き、全国平均が5万5695円となっています。
最下位の47位の鹿児島でも、3万7863円ですから、ベーシックインカムの月7万円構想なんて、絵に描いた餅です。
家賃だけで半分を占め、その他も考えると、病気などで働けない人は暮らしていけません。
「住宅手当(家賃補助)の金額をどれくらいに設定するか」の線引き、または「政府が借り上げて公営住宅とする」など、議論のポイントはあるでしょう。
2 記事からの引用・まとめ2
以下の記事から、引用・まとめをします。
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20211030-00265651
「家賃を何とかしてほしい!」 若者の訴えは政治にとどくのか?
戦後から続く住宅ローン供給による持ち家信仰が、以下の事象を形成させました。
バブル崩壊以降、頓挫し、賃貸住宅に長くとどまる「賃貸世代」です。
実際、持ち家率は平均値としては6割前後でほとんど変化していません。
ですが、世帯主が30~34歳では、1983年から2018年にかけて45.7%から26.3%へ、世帯主35~39歳では、60.1%から44.0%に低下しています。
その上、賃貸住宅市場では、より低所得の借り手が増えているにもかかわらず、低家賃住宅が減少しています。
そのため、家賃負担は重くなり、住居費負担率は1989年の12.2%から2009年には17.2%、2014年も17.1%となっています。
さらに、低所得層の若者に限定すると状況はかなり厳しくなります。
ビッグイシュー基金が行った、首都圏・関西圏に住む20~39歳、未婚の年収200万円未満の個人を対象とした調査によれば、以下のようになっています。
住居費負担率が30%を超える者が57.4%、50%を超える者が30.1%と、異様に重い住居費負担を強いられているのです。
重い住居費負担を避けるため、全体としては親同居の割合が非常に高くなっています。
国勢調査(2015年)によれば、未婚の若者一般の親同居率は63.3%ですが、ビッグイシュー調査では77.4%にも上っています。
ここで、親ガチャ問題が関係してきますが、詳しくは記事をお読み下さい。
ここからは各党の政策を見ていきます。
住宅手当については公明、立憲、れいわが掲げており、共産は住居確保給付金の拡大を主張しています。
また、公的住宅については、立憲とれいわが、空き家や民間住宅の借り上げによる拡充、社民が住居喪失者に空き家を活用することを掲げています。
日本では持ち家取得が推進され、公的住宅の整備は非常に限定的にしか行われてきませんでした。
「公的住宅の貧弱さ」は国際比較を通じてもわかります。
2018年のデータによれば、公的住宅の割合はオランダで37.7%、デンマークで21.2%、イギリスで16.9%に対し、日本はわずか3.6%に過ぎません。
なお、自民党、国民民主党、日本維新の会に関しては、残念ながら住居政策の明確な記載がみあたなかったとのこと。以上、ここまで。
引用・まとめの1番目の記事と、2番目の記事では、党の政策に関して、ちょっと内容が違うようですね。
公的住宅の案(空き家や民間住宅の借り上げも)は、住宅手当(家賃補助)より、僕の「集合住宅案に近い」です。
具体的な数字、例えば、住居費負担率の増加、未婚の若者一般の親同居率の高さ、日本の公的住宅の割合の低さ、などから、「僕の集合住宅案はけっこう筋のよい案だったのかも?」と推測します。
ですが、集合住宅だと、「老化が進む」というデータもあります。
僕はあくまで、議論のたたき台としての案を出しているだけです。
数字の裏付けなどなく、調査方法も分かりませんが、アイデアの方向性などに関しては良い線を行く場合が多いかもしれません。
ではこの辺で。(3679文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。





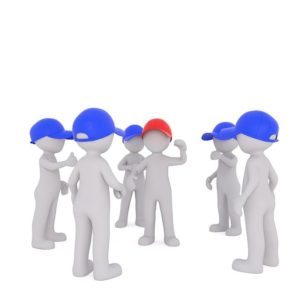




コメント